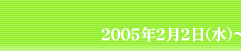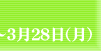|
 |
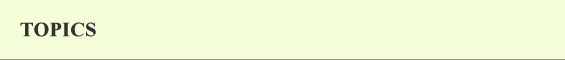
フォルクスビューネ・レポート
「終着駅アメリカ」観劇記 |
田原奈穂子 (劇場研究・舞台美術) |
ベルリンのミッテ地区、かつての東ベルリンの中心部アレクサンダー広場のすぐ近くに「ローザ・ルクセンブルク広場のフォルクスビューネ」はある。地下鉄2号線のローザ・ルクセンブルク広場駅で降りれば劇場は目の前なのだが、地下鉄8号線のワインマイスター通り駅からミュンツ通りを歩いていくのが私のお気に入りだ。この辺りには、「石のベルリン」と呼ばれた時代をしのばせる19世紀建造の古い建物と、1950年代から60年代に東独政府のもとでつくられたプラッテン・バウと呼ばれる鉄骨とコンクリートパネルで作られた建物が混在し、ベルリンの中でも独特の雰囲気がある。現代美術を扱うギャラリー、ブティックや雑貨店、レストランやカフェも多い。ローザ・ルクセンブルク通りの角を曲がると、行き止まりのアイストップとして目に飛び込んでくるのが、
「OST(東)」と青く輝くネオンを屋根に載せたフォルクスビューネだ。正面に6本の柱を持つファサード、左右対称でどっしりと落ち着いた佇まい、その手前のローザ・ルクセンブルク広場に立っている劇場のシンボルマーク「足のはえた車輪」、そして開演を待つ人々が待ち合わせや喫煙のために外に出て広場でおしゃべりしながらたむろしている様子が見えてくると観劇への期待は一気に高まる。
劇場のエントランスホールは人であふれている。ここは静かに観劇するためだけでなく、思想の刺激を求めて人々が集まってくる場所なのだ。年間約250の演劇公演だけでなく850にも及ぶ関連イベントが劇場内のさまざまな空間を利用して催されている。芝居の観客こそティーンエイジャーから高齢者まで幅広いが、関連イベントを含めると来訪者の70パーセントが若者たちだという。
チケットは10〜30ユーロ(約1300〜4000円)、学生・失業者・年金受給者等は半額だ。フォイエでは公演のパンフレットが売られている。パンフレットといっても公演のタイトルとキャスト・スタッフの名前が両面に粗く刷られた藁半紙一枚だけで、値段は50セント(約70円)。しかしその文字のフォントや紙の質感がどことなくカッコいい。フォイエからホールに入るとまず見えるのが舞台ではなく観客席だ。入口扉が舞台の脇、傾斜のついた観客席の一番低い位置にあるため、観客は自分の席を目指して傾斜を上っていかなくてはならず、必然的に舞台には背中を向ける。ホールに入るとすぐ他の観客の後頭部越しに舞台の様子が見えるほかの劇場とは違い、自分という個人と舞台が対面するのではなく、自分が舞台に対面する集団の中の一人であることを自覚させるしくみがさりげなく仕掛けられている。
私がはじめてこの劇場に足を踏み入れたのは2000年11月、ベルリン・プレミア直後の『終着駅アメリカ』、フランク・カストルフ演出&ベルト・ノイマン美術によるアメリカドラマシリーズの第一作だった。1999年に世田谷パブリックシアターで当時フォルクスビューネのドラマトゥルクだったリリエンタールを迎えてのシンポジウムがあり、「フォルクスビューネ」「カストルフ」という名前を聞きかじっていたので、ベルリンに行くからには一度観てみようといった軽い気持ちであった。『終着駅アメリカ』を選んだのもT・ウィリアムズの『欲望という名の電車』のアダプテーションだということならば言葉がわからなくても何とかなるだろうと思ったからにすぎない。しかしドイツ語の先生からは「あそこの劇場は挑発的で、クレイジーな人がたくさんいるので気をつけてね!」と言われ、チケット売り場のお兄さんはピアスだらけのスキンヘッドで強面。ほとんど何の前知識もなく、ドイツ演劇について勝手に政治的で真面目で難しそうで硬そうで…といったイメージを抱いていた私は、何か違うと感じつつも座席に向かう。そして席に着くなりまず舞台装置に目を奪われてしまった。日本の公団住宅の一室を、ベランダの窓から覗き見ているかのような部屋そのもの(テレビ、台所、バスルーム付き)がそこにあった。芝居がはじまるのも突然だ。登場人物たちが入ってくるなり弾き語りでルー・リードの<パーフェクト・デイ>を歌いだす。
舞台の上に設置された電光掲示には「五月はじめのたそがれどき。空は…」というト書きの引用が流れる。そこからは先はあっという間だった。休憩なし2時間半の公演が終わった時には私は興奮していた。とにかく面白い。上演されているのは確かにテネシー・ウィリアムズの『欲望〜』で、各エピソードも場面構成も戯曲を活かしているが、舞台上で起きていることはこちらの予想もつかないようなことばかりで眼を離す隙がない。次から次へと歌い、踊り、演奏し、とび跳ねる役者たちのパワーに圧倒される。音楽も印象的だ。ブランチの頭の中に流れるポルカはここでは<ワルシャワ労働歌>に置き換えられ、スタンリーが口ずさむのは対照的に一昔前のアメリカン・ロック、腹の出た中年男たちはポーカーをしながらブリトニー・スピアーズでハモる。
電光掲示板には舞台で起きていることとは関係ないことのように場面が変わるごとにト書きが引用され、文字が流れる。舞台と電光掲示されたテクストが交わるのは、掲示板の文字が読み取れないほど早くなった時だけだ。登場人物の全てがどこかおかしい。ポーランドで連帯に身を投じた時代の思い出話を繰り返しては家庭内暴力を振るうスタンリー、真面目な話をしながら目玉焼き作りにこだわるステラ、ひたすらギターを演奏するスティーヴとフランス語をまくし立てるユーニスの隣人夫婦、極度のマザコンのミッチなどに囲まれていると、<ワルシャワ労働歌>の幻聴に苦しむブランチがむしろまともに見えてくるほどだ。ブランチがステラに「あなたの夫は動物だわ」と言えばゴリラの着ぐるみを着たスタンリーが入ってくるなど、悪ノリも多用されている。
小さなテレビはカメラで監視されたバスルームの中の様子を映し出し、最後には舞台セットの「部屋」を使ったサプライズが待っている。拍手喝采カーテンコールの後、劇場を出る人たちの波に混じるとあちらこちらから、舞台で今さっきまで流れていた歌を口ずさんだり、興奮しながらおしゃべりするのが聞こえてくる。寒くてたまらない冬のベルリンでフォルクスビューネの周りだけ人の熱気で少しだけ温かくなったように感じられた。
|
PRATER
フォルクスビューネが運営している、もうひとつの劇場 |
それから4年がたち、その間何度も『終着駅アメリカ』を観た。連夜劇場に通い、他のレパートリー作品を知り、ドイツ・ベルリンの社会・文化・歴史的背景についての知識が増え、セリフも聞き取れるようになるにつれて、カストルフが描き出そうとした現在のベルリン社会が抱える問題点を少し読み取ることが出来るようになった気もする。一方で一見ハチャメチャな演出に織り込まれたコンテクストの膨大さを垣間見て、ドイツ演劇を普通の日本人が理解するのは不可能だとも感じさせられる。しかし舞台を観るのに頭で理解できるかどうかなんて関係ない。だって手狭なのに設備は整った住居を模した、君臨するテレビやカラフルなファッション、アメリカンポップスに彩られた舞台は東京育ちの日本人の私にも、十分に身近で身につまされる世界だったのだから。そして、「現実をイミテーションするのではなく、現実の中に存在するイミテーションを舞台上に引用する」手法で現実世界の演劇性と演劇におけるリアルを対比してみせるノイマンと、「リアリズムではなくリアリティ」を重視するカストルフの演劇が現実を映す鏡なら、このメディアや仮設物や大量生産品にあふれた現代社会で演劇において何がリアルでありえるのかという問いかけは、ドイツに限らず世界中の演劇に対する問いかけであるはずなのだから。そしてなによりこの舞台はチャーミングな俳優たちのパワーに満ちたライヴ感あふれているのだから。
カストルフとノイマンによる演出・美術コンビの作品を観るたびにまず惹き起こされるのは感動でも感心でもなく興奮だ。怒鳴り合いと静けさ、ユーモアと真剣さ、過剰さとシンプルさが同居しころころと入れ替わり、感覚はすぐ許容量いっぱいになってしまう。決して作品の世界に引き込まれているわけではなく、現実との地続き感は頭のどこかで十分に意識しているはずなのに、冷静に見ているというわけでもない。この奇妙な感覚でごちゃごちゃになった頭を抱えて劇場を後にする。それはフォルクスビューネのポスターで埋め尽くされたローザ・ルクセンブルク広場駅から地下鉄へ乗りこんでもしばらくは冷めない。そして舞台に仕込まれたクスリの成分は、気付かないうちに刺さった棘のように、翌日以降にじわじわと効いてくる。興奮のうちに大して気にもとめなかったデティールから舞台の記憶がよみがえり気になって仕方がなくなる。次から次へと疑問が湧き、また劇場に行きたくなってしまう。そして気付いてみると刺激を求めてフォルクスビューネに通いつめる「フォルクスビューネ・ジャンキー」になっているのだ。カストルフの新作はアンデルセンの童話『雪の女王』、楽しみだ。
|
|
|
|
|
|