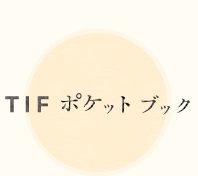BeSeTo演劇祭、Shizuoka春の芸術祭、利賀フェスティバルなどの国際演劇祭に招聘される気鋭の演出家、倉迫康史。にしすがも創造舎のレジデント・アーティストとして、東京国際芸術祭でも作品を発表してきた。
演劇を通じて「近代」にまつわる諸問題の見直しと提言を行うだけでなく、豊島区民を対象にした「読み聞かせ実践講座」(文化庁「文化芸術による創造のまち」支援事業)の講師を務めるなど、地域に開かれた演出家としての活躍も目覚しい。
東京国際芸術祭2007のオープニング作品『肖像 オフィーリア』の発表を10日後に控えた倉迫に、これまでの取り組み、演出についての考え、そして今回の作品について話を聞いた。
(1/21(日)にしすがも創造舎にて)
本インタビューの内容は、こちらのPDFファイルで読むこともできます。
ファイルをダウンロード

日本人がひとつ誇りに思えるような何かを作りたい
――最初に倉迫さんの演劇的なキャリアについてお伺いしたいのですが、まずは演劇に携わるようになった経緯について教えてください。
始めたのは遅いですよ。大学を卒業してからなので。
――大学在学中ではなくて?
ええ。大学4年の1月の終わりに演劇をやろうと決めて、2月の頭に大学院の試験があったのを受けるのをやめて、急遽卒業することにして…だから突然ですね。
どうしてそういう風に思ったのかというと、僕らが大学3年の頃が1990年〜91年で、ちょうどバブルがはじけた時だったんですね。それまでは先輩とかが「証券会社に入りました」とかいってブイブイいわせてるみたいな感じで、就職活動なんかに行くと本当に超売り手市場。僕は早稲田の政経だったので、まあどこでも入れるだろうというような感じだったわけです。いわゆる戦後経済がひとつのピークを迎えた時期。
で、それが崩壊して、非常に社会全体が落ち込んだ雰囲気になっちゃったんですね。それが気持ち悪いなあと思って。経済大国でなくなっちゃうとこんなに活力が落ちるのはいかがなものかな、と考えました。そうすると例えばアルゼンチンとかはいま経済破綻しているんですけど、サッカーみたいなものがあるだとか、イタリアはモードみたいなものあるだとか、「この国はこの文化が世界のトップレベルにあるんだ」ということを国民が思えば、一応それを誇りにして生きていけるだろうと思いまして。
10年くらい前から共産党なんかが「文化大国」って言いはじめたけど、そこまで明確な政治的な意図ではなくて、とにかく何か日本人がひとつ誇りに思えるような何かを作りたいなあと思ったんですね。そういうところで働きたいなあと思って。今だったらアニメとかマンガなんだろうけどね。
現代演劇、まあ小劇場みたいなものは見てたんですね、大学生の時から。それもあって、なおかつ大学2年の終わりかな、春休みに1ヶ月くらいニューヨークに行ってぶらぶらしてて、その時ブロードウェイとかオフ・ブロードウェイとかオフ・オフ・ブロードウェイとか観に行きまして。やっぱりエンターテイメントとしてはアメリカというのはすごいなと思ったんだけど、ひょっとするとある種の哲学性であったりとか精神性みたいなところにおいては、日本の演劇というのは世界に通用するんじゃないかなと思ったんですね。
で、そのことを大学3年の終わりくらいに思い出して、じゃあ現代演劇を日本の誇りにしていくには、どういう風に育てていけばいいんだろうか?ということを考えたんですね。で、それには「国際的な演劇学校を作ること」だと思った。世界中から俳優や演出家が演劇を勉強しに来る学校を作ればいいんだと。
そういう学校を作るにはどうしたらいいんだろうと考えた時に、文部省の直轄で作るとなると法律もあって大変なので、外務省直属で国連大学的な、国際的な演劇学校を作ればおもしろいんじゃないかなと思って、大学の時に外交官試験を受けているんです(笑)。それで当然落ちているんですね、受かっていたら今それをやっているはずなので(笑)。
落ちてしまったので、まあ大学院に進学して修士課程が終わるときにもう1回受けよう、それがダメだったら教育分野の方に行こうと思ってました。「国際的な演劇学校」だから「国際」をとるのか「学校」をとるのかという選択肢があったんだけど、大学4年の時にふと、「やっぱり現場に行かなきゃダメなんじゃないの?」と思いまして。
29までは外交官試験は受けられるし、後から大学院に入りなおすこともできるので、20代の修正がきくうちに、現場を一旦くぐっておこうと思って、急に現場に入りました。
だから役者をやりたいとか、そういうのじゃなく始めているんですね。表現をしたい欲求があるとか、そういうのじゃなくて、動機はたぶんアーツマネジメントを勉強している方々に近いと思いますね。アートとか文化というものが、どうやったらこの日本の国にいい形で関わっていけるのかとか、どうしたら社会を良くしていけるのかと考えた時に、演劇を使おうという発想だったんです。
ただ、当時はアーツマネジメントとかいう言葉もないし、制作者 にスポットライトなんか全くといっていいほど当たっていない時代だから(笑)。
当時は夢の遊眠社 が解散したり、第三舞台 が活動停止したり、80年代演劇ブーム最後の時代で、作・演出をする人が人気者になって動員を増やしていく時代で、自分がそういう風になるというイメージはあまりできなかったんだけど、ただ入り口がそこしかなかったんですよね。しょうがないから、とりあえず大学を卒業してから1年間は養成所に行ったんですよ。役者やりたくないのに(笑)。
でも役者にしか門戸が開かれていないから、1年間やって、その間にどこか演出助手で入れるところを探そうと思って。
――それまでは全く演劇の経験はなかったんですか?
本格的にはないですね。ただ、演劇は好きだったんですよ。高校生3年の時に文化祭があって、受験生なのにすごくお祭り好きな世代で、「演劇作ろうぜ」とか言って、よくわかんないけどいま東京じゃ『レ・ミゼラブル』が流行っているらしいぜ、じゃあそれやろうぜ、なんて言って台本書いたり(笑)。
あとやっぱり小学校の時に芝居とか人形劇とかよく観てましたね。もう自分の完全な原体験として、劇場という場所が好きなんですよね。映画館も好きなんだけど、やっぱりそこに行って何かこう特別な場所、非日常的な空間に身を浸して物語を観るっていう、その快感はずっと覚えていたし、それがおもしろかった。
年間200本観て、一番おもしろかったのが山の手事情社
――大学を卒業して、養成所に入った後はどうしたんですか?
わりとクレバーな人間だったので、スタートが遅いというのはわかっていたし、早稲田の同世代なんか演劇研究会とか入ってがんばっていたのは知っていたので、同じような方法論ではいけないなと思ってました。スタートが遅いぶんだけ、自分の環境を24時間演劇漬けにしてしまわなきゃダメだなと思っていて。
そしたらたまたま「ぴあ」の、票券を作るチケット営業部というところがバイトを募集してまして。そこに「演劇でやりたい」と言って申し込んだら、そこにたまたま当時の名物社員のキタノさんという人がいてですね、大川興業出身の人なんですけど、モヒカンというか弁髪みたいな頭してて(笑)。向こうは弁髪で、僕はその当時スキンヘッドだったんです(笑)。その彼がすごく僕のことをおもしろがってくれて、ぴあの小劇場担当になりました。雑誌じゃなくてチケットを売る方だったので、劇団の制作の人とかが来るわけですよ。「チケット売りたいんですけど、どうしたらいいでしょうか」とか相談受けたりして、逆に本誌の方には「今、この劇団が売れそうだから雑誌で取り上げたほうがいいよ」とかアドバイスしたりして。
それで月曜日から金曜日まで働いてて、当時は月、水、金の夜と土曜日の午後に養成所に行ってたんです。土曜日は行かなくてもよかったんだけど、「お前はヘタクソだから来い」って言われて行ってた(笑)。で、週4日稽古して、残り3日間空いてる日は全部芝居を観に行ってました。ぴあで働いてたので、招待券がいっぱい貰えるんですよ。
それで1年間で200本くらい芝居を観て、一番おもしろかったのが山の手事情社ですね。この劇団はおもしろいなあと思っていたら、ちょうどそこで演出助手を募集していたんです。迷うことなく応募して、養成所が終わった次の月から、山の手事情社の演出助手として入りました。
ぴあは1年以上続けたんだけど、社内で「倉迫を社員にしよう」という動きが起きて、すったもんだの末「辞めさせてください」って言って辞めました。ぴあを辞めるにあたって、食っていかなきゃいけなくなったんですけど、僕は大学時代に「テレビ放送研究会」っていうサークルに入ってまして。要はテレビ業界で働きたい人間が集まってくるサークルだったんですけど、例えば今だと『木更津キャッツアイ』を作った金子っていうのは僕の1つ下のサークルの後輩で、『あいのり』とか作っている堀田延は1つ上の先輩で、2つ上の先輩は今も一緒にV6の岡田准一君のラジオ番組を作っている放送作家で、3つ上の先輩は武豊のルポルタージュを書いてる人もいたりして…という感じで、業界と直結しているサークルだったんですね。
僕は放送作家がきらいだったから(笑)、大学時代は業界では働いてなかったんですけどね。ただ、学祭の時に自主製作の番組を作って、大隈銅像の前にでっかいモニターを9台くらい置いて放送を流すということをやったりということはしていたので、「じゃあ放送作家になろうか」と思いまして。ツテはあったので「こういう事情で放送作家をせざるを得なくなったので、仕事まわしてください」って言ったら、すぐラジオの仕事がレギュラーで入ってきて…それからはずっと放送作家と演劇の2本立てですね。

Ortは基本的に、自分がやっていた劇団のアンチだった
――山の手事情社では、演出家を志して活動していたんですよね。
そうですね。本当は山の手には3年くらいいたかったんですけど、1年半くらいしかいられなかったんですね。
それはなぜかっていうと、養成所の同期が旗揚げしてくれって言ってきたんですよ。みんな、文学座とか入りたかったんだけど入れなくて、「自分たちでやろうよ」と言ってきたんです。実は養成所時代に自主公演をやったんですね。それが割と評判良かったっていう記憶がみんなにあったので。だから「劇団を作ってくれよ」と言われて、「そうかー」と思って(笑)、24の時に山の手を辞めて劇団を作りました。その時は作・演出でした。劇作家でもあったんです。
――それ以降は、ずっとその劇団で活動していたんですか?
それから4年半くらいはその劇団をやった。やったんですけど、書く才能がないなあと思って。劇作家としての才能がない(笑)。
実は、そこそこお客さんも入ったし評判も良かったんですけど、同世代の集団を率いなきゃいけない、リーダーでなきゃいけないというのがやっぱり無理だったし、演出家として世界を描かなきゃいけないっていう時に、未熟な世界でしかないわけですよね。東京の若者の孤独感を描くとか、都会で傷ついている姿を描くとか、自分探しを描くとか、というようなことしか書けなかった。そうするとネタって尽きるんですよね、3本くらい書くと(笑)。あとは拡大再生産みたいになってきちゃうし、どっかでパクリみたいになってきちゃうんです。「インスパイアされてます」とか言いつつ、これは明らかにパクリだなというのが出てきたりして…。
でも当時は作・演出以外考えられなかったんです。演出だけやるっていう人はほとんどいなかった。基本的に小劇場というのは作・演出をやって、そいつが劇団の主宰者っていうのしかサクセスロードがなかったんですよね。
で、まず人が辞めたんですよね。男5人、僕入れて6人で旗揚げしたんですけど、コメディアンになりたい奴、映像俳優になりたい奴、声優やりたい奴がいて、まずこの3人が早々に辞めた(笑)。(劇団を)始めて2本くらいで。あとの2人は舞台をやりたがってたんだけど、そのうち1人が家の事情で辞めざるを得なくて、もう1人はNHKの大河ドラマに出たいって言ってて、事務所に入って一応端役をつかんだんです。で、「舞台続けられない」って言って辞めちゃったんですよ。
そうすると…心が折れるんだよね(笑)。こいつらに「旗揚げしてくれ」って言われて旗揚げしたのに、気づいたら僕だけで下の世代は女優ばっかり。まあその3期生に三橋*がいたりしたんだけど…(笑)。
*三橋麻子(女優)。『肖像 オフィーリア』ではガートルード役を演じる。
28の時に「もう続けられないな」って思って、いったん劇団を辞めて。それで演劇を辞めるかどうか考えたときに「まだ試していないことがある」と思ったんです。
それで、29になってこれから1年間どうしようと考えていたとき、ちょうど平田オリザさんや宮城聰さんが「若い演劇人のための集中講座」という伝説の講座を開いて、そこに参加したんですね。
そこで初めて助成金のこととか、公共劇場がどうなっているかとか、日本の芸術文化振興基本法が出来上がっているプロセスとか、初めて知ったんです。劇団を運営するのはこういうことだっていうことも初めて聞いたし、僕はそれまで演劇界に友達が誰もいなかったんです(笑)。山の手は別だけど、演劇研究会にいる人たちだから成り立ちが全然違うしね。
その講座で初めて夏井くん*とか、オレンジの横山さん*とかに会って、そこで出会った人脈がいまだに脈々と続いているかな。その面子が一応改革を起こしたっていう感じはあるから。
それもあって、1年間考えて、こういうスタイルでやれば演劇続けられるし、ひょっとしたら注目されるかもしれないって思って始めたのがOrtなんですよ。
Ortは基本的に、自分がやっていた劇団のアンチだったんです。劇団でやっていたことと全く真逆のことを全部していこうという作戦を立てて、30の時に始めました。
*夏井孝裕(演出家/reset-N主宰)。2007年1月現在、文化庁の平成18年度新進芸術家海外留学制度の研修員としてフランスに滞在中。
*横山仁一(演出家/劇団東京オレンジ主宰)。
――それは演劇的なことだけでなく、興業や組織の形態などについてもということですか?たとえばカンパニーではなくユニットとして活動するということなど…
まずユニットっていうスタイルにしたのは、とにかく(演劇を)続けていけない最大の理由は経済的なことで、何に(お金が)かかるかっていったら小屋代なんですよね。あと装置を作るとか。ということは、舞台美術家をユニットに入れりゃいいんだと思って(笑)。
それで声をかけたのが伊藤雅子*。初めて伊藤雅子と会ったのは彼女が大学4年生の時だったんだけど、当時はくすぶってて、「じゃあやりたいことやるために僕といっしょにやろうよ」って言ったら「やる」と言ってきた。
*舞台美術家。Ort-d.d『サーカス物語』(2005年10月)などの舞台美術を担当し、2005年度伊藤熹朔賞新人賞を受賞。
それで、僕と伊藤と、あともう1人女優がいて、彼女は前の劇団の女優さんだったんだけど、そいつもくすぶってたから3人でやろうと。で、劇場じゃないところでやろうと思った。たぶん今でこそみんな使うけど、阿佐ヶ谷のヴィオロン(東京・阿佐ヶ谷の名曲喫茶)とかで初めてちゃんと芝居したのは我々だったし。
お金をかけずに芝居を打つ、そのためには削れるものは削ろうと。だから劇場である必要はないよね、と。あと、音楽使わなきゃ音響さんいらないよねっていうこととか(笑)。だから最近でこそ音響スタッフを入れているけど、当時は音楽も一切なかった。で、書くのが大変なら書かなきゃいいじゃんと(笑)。それに冷静に考えると、普通、どこの馬の骨が書いているかわからない芝居を観に行かないだろうと。
それで1番最初にやったのが、森鴎外の『舞姫』であり、2作目が夏目漱石の『こころ』なんです。

教科書に出ている名作をやろうと思ったんです。
誰もが知っている名作を、しかも戯曲じゃなくて小説を演劇的に処理することを見せようと。そしたら原作のファンが観に来てくれるかもしれないということと、劇場でないところ、変な空間でやるってことで興味持ってくれる人が来るかもしれない。そういう人たちの中で話題になっていけばいいと思ってました。
僕はマーケティングの方法論として、マーケットに飢餓感を起こすということをやりたかったから、わざと情報を押さえた。当時はほとんどなかったことだけど、限定40人、完全予約制で当日券はありません、とか。
で、遅刻すると入れないんですよ。なぜなら受付が僕しかいないから(笑)。受付が僕で、照明をいじるのも僕なので、始まるとドアを閉めて「他のお客様のご迷惑になるので入れません」って。
だからある種、排除するということをやりました。一般のお客さんなんて絶対観に来ないから、構図から(人が)集まるようなシステムをまず作る。演劇マニアなり、そういうちょっと変わった連中に受けるというか、そこのアンテナに引っかけて、そこからは口コミで広げていこうという作戦でした。
「ささやきの演劇」というスタイル
――当時から、日本近代文学を取り上げると決めていたんですか?
それは話題を作りやすいってこともあったんですね。例えば演劇ファンにとっては『動物園物語』ってパッと浮かぶけど、普通の人にはわからない。でも『舞姫』と聞けば、「ああ、何かかわいそうな女の子が出てくるやつね」とか、『こころ』だったら「何か死んじゃうやつでしょ?」とか(笑)、なんとなくみんなイメージがあるから。そういう理由で始めていって、もう1つは「語り」ということに興味を持ち始めたから。
劇団の一番最後の作品で、やろうとしてやらなかった作品がありまして。『ささやきと人形的所作による集中線』というタイトルで、台詞は全部ささやくように喋る、動きは全部人形みたいに動くという芝居を作ってみたいと思って、劇団員に提案したら猛反対にあった(笑)。
それが直接的な原因で劇団は解散してるんだけど、一緒にやろうとしていた女優はそれをおもしろいと思ってくれていて。
ささやくように台詞を喋りながら身体は人形のように動くというのがすごく美しいと当時は思っていて、日本の文学ってそれをやるのはちょうどよかったんです。
劇場じゃない狭い空間でやるから、お客さんが近くにいるから大きい声を出す必要がない。で、音楽を使わないから台詞を全部音楽にしなきゃいけない。台詞に音階をつけていくということも含めて、そうすると語りに抑揚をつけていかなきゃいけない。日本語の処理の仕方が、単純な会話の処理の仕方じゃなくなる。
なので、そういう外的な要因によるのと、もともと語りに興味を持っていたというのがドッキングして、それで初めて自分たちのスタイルが出来た。
――そういったスタイルを築いてく上で、影響を受けたり、参考にした作品はありましたか?
人形浄瑠璃が好きだったんですよね。人形劇とか…、たぶん僕は人形フェチなんですよ(笑)。いまだに、この間韓国に行った時も、人形博物館に行った時なんかテンションが上がってしょうがなかった(笑)。だからちょっと変態なところがあって、人工的な質感がすごく好きで。人形浄瑠璃とか、無機物なのにすごく色っぽく見えるとかね。
さっき言った「若い演劇人のための集中講座」に宮城さんがいて、ク・ナウカを観に行ったら「これじゃん!」と思った(笑)。自分が考えていることと全く同じようなことをやっているなあと。
ただ、宮城さんの場合は、どちらかというといかにドラマチックにしていくか。あの人は東大出身で、駒場小劇場という大きな劇場でやるということで、どうしたらスケールのでかいことが出来るかということをやっていた。
逆に僕はスケールをどこまでミニマムにできるか、ということに比重を置いていた。だからク・ナウカを初めて観た時はすごく衝撃を受けたというか、とても共感しました。
Ortが始まると同時に、利賀の第1回演出家コンクールが始まって、そこに参加したんですが、阿部公房の『棒になった男』が課題戯曲でした。40分くらいの戯曲だったんだけど、もう全編ささやいていて、聞き取れるか聞き取れないかのギリギリのところをコントロールしていくというものでした。
それで終わった時に宮城さんが「いやあ、これは問題作だねえ」と言って出てきた(笑)。で、宮城さんと鈴木忠志さんが評価してくれて。賞は取れなかったけど、その翌年の「Shizuoka春の芸術祭」に呼ばれました。
その時に、自分がやっていることは割と間違っていないんだなと思ったし、逆にいろんな発展形が考えられるのだと。
演劇の「深さ」ではなく「広さ」を獲得していく
――Ortでは狭い空間の中で、俳優が台詞をささやくように喋るという「ささやきの演劇」を展開していたということですが、現在の倉迫さんはにしすがも創造舎などの大きな会場で公演するなど、違ったスタイルの演出を行っています。それは「ささやきの演劇」から発展していった結果と考えていいのでしょうか?
発展してますね。その理由はいくつかあります。
まず、緊張感だけで芝居をしていくという時に、ささやきを出来るというのは、役者にはすごい力量が必要なんです。というのは声が小さいだけじゃ駄目で、圧倒的に声が出て、なおかつ抑揚をコントロールできる人間じゃないと、実はミニマムのコントロールってできないんです。それがわかって、これは大変なことだと思った。
それから、お客さんの集中力も60分しか続かない。「ささやきの演劇」は美学的には非常に美しくて、この緊張感は好きなんだけど、これがどういう風に展開していくのか、どうやって普遍性なり一般性を獲得していくのかというところで、すごく考えました。

それで「ささやきの演劇」を捨て始めた時に、割と忠告されたりもしたんです。要は、ある種特殊な演技法なので、様式を作っていくためには、集団を作って、少人数でも俳優をトレーニングして訓練していく、という風にしていかないと、様式の完成度が上がらないじゃないかと、いろんな先輩の演出家から言われて、確かに「それはその通りだ」と思ったんです。ただ、自分がその道を選ぶのかというところで、はたと立ち止まって。
ここで、最初に「なぜ演劇を始めたのか」ということに結びつくんだけど、そもそも芸術、アートとしての作品を作るということが第一義ではない。つまり自分の好きな作品を好きなように作って、その自分の好きなように作った作品を愛でるために始めたのではない、と思ったんです。
僕のやっていることというのは、今ここ(にしすがも創造舎)でやっていることもそうだけど、演劇というツールを使って、たとえ薄味になったとしても残る「演劇の良さ」を、どれだけ多くの人に伝えていけるかだと思いました。
だから、よく「僕は”前衛”を辞めた人だから」と冗談で言ったりするんだけど、前衛というのは芸術の「深さ」みたいなところを果敢に切り拓いていく人だと思うし、僕がやっているのは、演劇というのがどれだけ「広さ」を獲得していくのか、開拓していくのかということだと自分では思ってます。
しかしそこはだいぶ葛藤があったんですけど、Ort-d.dにした時に腹をくくりました。
Ort(オルト)とはドイツ語で「場」を意味する。2000年から始まったOrtの活動は2002年をもって終了し、2003年からはOrt-d.dとして再スタートした。Ort-d.dはOrt das dritteの略で、「第三の場」を意味している。
Ortを始めて、「おもしろい」と言われて、演劇的な評価みたいなものが高まっていくと、やっぱり外部との接点がいろいろ生まれてくるわけですよ。どこかに呼ばれたりですとか。そうするとジレンマを抱えることになる。
自分がやっている、ある種先鋭的であろうとする、エッジが立っていることをやろうとすると、それは閉じていく。どうしても限定されたお客さんに向けたものになっていくんです。でも芸術家として、広い範囲の人に何かを発信しなきゃいけなくなってくる。ワークショップとかね。
そうすると自分の持っているものすべてが通用するわけじゃなくて、その中のどれが通用するか、どれを翻訳して伝えなきゃいけないかということになってくる。それをやってみようと思ったのがOrt-d.dです。
Ortの女優は反対したんです。彼女は、ある種の趣味でいいから、マイペースでやればいいじゃないか、自分のやりたい作品を無理せずやって、お客さんを300人とか400人入れて、赤字が出ない程度にやればいいじゃないかと言ってまして。それってとても正しいんですけどね。この国で演劇を続けるには。
伊藤(雅子)は徐々に頭角を現してきたので、ちょっと1人で本気で舞台美術に取り組みたいと言い出してきて。それぞれが3年くらいすると道が違ってきたんですね。
だから、じゃあ僕は演劇と社会をどう結びつけるかというのをとにかく試してみるよ、と言って始めたのがOrt-d.d。だからOrt-d.dはソロプロジェクトにして、全部自分で責任を取る形にしました。

にしすがも創造舎上演プロジェクトvol.1『サーカス物語』(c)萩原靖
1人1人と結びついていて、それが絆になっている
――現在でもソロプロジェクトという形態をとっているんでしょうか?
一応今年からカンパニー化するって宣言してやってましたが、じゃあカンパニー化するって何だよって言うと、普通に考えると「会社」ですからね。そういう意味では確固たる組織にはなっていない。
やっぱり、自分が劇団を以前に失敗していることもあるし、劇団の嫌な部分もいっぱい見ているので、どういう風な集団性を持つと一番いいのかというのは、いま一番考えていることですね。
Ort-d.dにして何が良かったかというと、Ort-d.dには僕しかいないので、僕と俳優、僕とスタッフは全部1対1の関係で結ばれているんです。ある組織図の中で、御大のように僕がいて、あとは上意下達みたいなシステムじゃなくて、僕が1人1人と結びついていて、それが絆になっている。
「倉迫が何かするなら駆けつけるよ」という人がいて、そういう人間的にも技術的にも信頼している人たちが、何かあると集まってくれる。
――映画製作のプロジェクトチームのような感じですね。
そうですね。そういうプロフェッショナルが集まってくれる。
以前は僕と1対1の関係だったのが、スタッフ同士、役者とスタッフ、あるいは役者同士の1対1の関係に結んでいけるようなシステムというか座組を作っていこうと思っていて、そのために人を育てないといけないなあと思って、それで去年はU-30プロジェクトをやってたんです。
それは演技を上手くするだけじゃなくて、人間同士のコミュニケーションというのはこういうことなんだよ、人と真っ当に付き合うっていうのはこういうことなんだよ、と教えてきたつもりです。そういう絆で結ばれている連中が、傍から見るとカンパニーに見える。非常に堅固な集団に見える。
外枠をがっちり固めて集団にするんじゃなくて、それぞれの人員を繋いでいるラインがすごくいっぱいあって、そこが強く結びついている、という風になるといいなと思っているんだけど、まあ理想論だよね(笑)。
――「劇団員」というわけではなく、同じ方法論を共有している個人の集まりということですね。
でも、外で名乗るときに、「フリーです」と言うよりは「Ort-d.dです」と言ったほうがいい場合は、そう名乗ればいい。「Ort-d.dです」と言うのが恥ずかしいんだったら(笑)、言わなきゃいい。
その辺は役者個人が決めればいいと思うんです。一律でこっちが要求することじゃないから。
役者が自分の人生の中で、Ortという名をどう使うかは役者に任せているし、そこは信頼してますから。

東京国際芸術祭2005『昏睡』(c)萩原靖
オフィーリアは何者なのか
――今回の公演『肖像 オフィーリア』では、太宰治の『新ハムレット』や小林秀雄の『おふえりや遺文』など、近代の文学者たちによって描かれた「オフィーリア像」をコラージュするとお聞きしました。
夏目漱石や島崎藤村も、小説の中の女性をオフィーリアになぞらえたりしていますが、彼らは一体オフィーリアの何に惹かれたんでしょうか?
あの人たちはね、勝手に自分たちのイメージを作っているんですよ(笑)。
オフィーリアというのは非常に印象に残るキャラクターなんだけど、原作を読めばわかるとおり、何者なのか全くわからない。非常に従順で、何色にでも染まる感じ。「あなた色に染まります」っていうタイプなんですよ(笑)。
お父さんに何か言われると「お父様に従います」、国王に何か言われると「王様に従います」、そうやって全部言いつけに従います、従いますって言って、それで最終的には男の事情に翻弄されて気が狂っちゃうっていう。で、それはたぶん、どこか儚いんですよね。
そんな風に、どこか清純な雰囲気があって。でも、シェイクスピアの台詞ってちょっとエロティックな部分もあるんですね。清純に見えるんだけど、実はハムレットともうやってるんじゃないか、処女じゃないんじゃないかっていう風に思えるし、逆にものすごく貞淑な人という風にも解釈できるし。読む人によっていかようにでも解釈できるんですよ。
ハムレットの苦悩というのは、文学者にとってはまさに自分のことなんです。親との葛藤とか、恋愛の葛藤ですとか。あれはある種、アーティストの苦悩なんですね。
そこに自分の悩みをシンクロさせたときに、オフィーリアっていうのは自分の理想像なんです。こういう女がオフィーリアだったらいい、俺にとってのオフィーリアはこれ!っていう(笑)。
たとえば『草枕』では、那美という女がオフィーリアにたとえられたりするんだけど、あれは全然!オフィーリアじゃないからね(笑)。
ある種、男にとって都合のいいように解釈されうる女ですね。ハムレットの原作の中でのポジションもそうだし、日本の文学者たちの中でもそうだし。そういう女性がどういう運命をたどるか。

John Everett Millais "Ophelia" 1851-52
僕がやっていることは、慰霊碑を建てるような作業
――今回の会場は、重要文化財の自由学園明日館の講堂ですね。この空間を利用してどのような演出をするのか非常に興味があるのですが、今回の公演に合った場所ということで、自由学園明日館を会場に選んだのですか? それとも、自由学園という空間を先に選んだのでしょうか?
空間が先ですね。僕は「何をやるか」っていうのは、割と空間からインスピレーションを得るんですよ。
重文(重要文化財)で(芝居を)やるのは2回目で、前にやったのは東博(東京国立博物館)だったけど、それは東博の表慶館を見に行ってから、「『四谷怪談』だな」と思ったんです。
もともと四谷怪談で天皇制の物語を書くとおもしろいなっていうのがあって、また大正天皇が成婚して(表慶館を)建てられたという大正天皇の運命を思ったときに、そう思ったんですね。場所の雰囲気と、そこの持っている歴史性。
その建物がなぜいま残っているか、どうやって建てられたか、その建物にはどんな思いが残っているかということをすくいとりたい。すくいとって作品を作りたい。
だから僕がやっていることは、たぶん慰霊碑を建てるような作業なんですよ。この場所にこういう慰霊碑を建てましょう、という。
ここに成仏しない魂がいるとして、この魂をどう鎮めるか、どう成仏してもらうか、どうやって魂をすくいとるのかというのをやるのがアーティストの仕事で、僕は劇場じゃない場所を選んでいる時は、その場所をどう「聖なるもの」として扱っていくのかということを考えます。
で、(自由学園明日館に)行って、見て…あそこは大正時代に出来た学校ということで、つまり近代教育というものが始まった場所でもあるんですよ。キリスト教の学校でもありますし。
太宰というのは結構キリスト教を扱っていたこともあり、明治・大正・昭和の中で、キリスト教がどう日本人の中に入っていったかということを扱うのもすごくおもしろいなと思って、「近代教育とキリスト教の普及」みたいなことをキーワードに、ハムレットをできないかなと思っていたんですね。
その時は写真や外観だけしか知らなかったんだけど、その後にちゃんと中を見に行ったら、女学校だったんですね。そこで講堂の中に入ったら、いろんな女の子が自分の目に映ったんですね。あちこち座っていたりして。幻なんですけど、そういうのが見えて。何だろうと思って、あ、これはオフィーリアだなと。そこらへんからいきなりハムレットからオフィーリアに飛んだわけです(笑)。その時に自分が見た幻がすごく絵になっていたわけですよ。そこから『肖像』というタイトルが出てきました。
――女学校だから『女生徒』(太宰治)というわけじゃなかったんですね。
最初から、ハムレットよりも『新ハムレット』が先にありました。太宰の『新ハムレット』と志賀直哉の『クローディアスの日記』は前から読んでいたんです。それで、同じハムレットを題材にして作品を書いた太宰と志賀直哉が、文壇上でも大喧嘩していたのも知ってて、おもしろいなあと思っていて。
それは『冬の花火、春の枯葉』をやっていたときからおもしろいなと思っていたわけです。で、せっかく『冬の花火、春の枯葉』をやったので、『新ハムレット』もやりたいなと思っていて。ハムレットについて調べていったりイメージを固めたりですとか、あと以前に『ハムレット オフィーリア・プログラム』をやっていたこともあって、自分の中でいろんなことが繋がっていったんです。
――『新ハムレット』に出てくるオフィーリアは原作とは違って、非常にしたたかというか図太い感じの女性ですよね。
あれはたぶん普通の女の子なんですよ。普通に妊娠して、上手くやっていくタイプ(笑)。
――『新ハムレット』では、ガートルードの方が儚い女性に見えます。
そうですね。でもあのガートルードっていうのは、オフィーリアの成れの果てでもあるから。
要するに、妊娠しちゃって、普通になること、母親になることを選んでしまった人たちがどういう風な絶望を辿るかということを描いてるんです。
だから『新ハムレット』のオフィーリアが幸せになるかどうかはわからない。

東京国際芸術祭2006『冬の花火、春の枯葉』(c)萩原靖
演出家の定義をもっと広くしたほうがいい
――最後の質問ですが、倉迫さんのこれまでの活動や目指すところをお聞きしていますと、非常に社会に目を向けていて、そのための活動を沢山なさっていますね。
「演出家」という定義にあてはまらない、もっと社会的な役割を担おうとしているように思えますが、ご自分ではどう思われますか。
でもね、ヨーロッパの演出家というのは十分に社会的だし政治的なものですよ。
それはなぜかというと、公共劇場に付属している劇団を持っていて、劇場は人が集まる場所である、広場であると考えている。そういう場所である公共劇場はどんなことを発信していくのか、というのは当然考えていかなきゃいけないことなんですよね。
僕は、演出家の定義自体をもっと広くしたほうがいいと考えていて、演出家というのは、作品を演出するだけじゃなくて、街を演出するだとか場所を演出するだとか、自分の居場所を演出するっていうことも含めてね、そういうこと全部を含めての演出だと思うんですね。
社会を演出していくこともそうだと思うし、それができないとダメだなと思うのは、だって演劇は社会の映し絵であるし、世界を切り取るものであるということは、当然社会に対して興味をもっていなきゃいけない。
あるいはいま現在の日本人なら日本人にちゃんと響くもの、社会的な問題性だとか「今、こういう哲学が欠けているんじゃないか」ということを作品にこめていかなきゃいけないわけだから、それに対する接点を持たなきゃいけない。
――一般の「演出家」に対するイメージの方が狭いということですか?
狭いんだと思いますね。「(演出家は)演出だけやりゃいい」ってことの意味の方がわからない。
作品を作るってことは作品を発信するということとイコールだし、それがどんな影響をもつかということも考えるし、その作品を作るときには何をこめるかということも考えたときに、全部社会的なことを考えなきゃいけないもんだっていうのがある。
趣味的に作品を作るのであれば、己の趣味だけ追及して、「これが私の美学です」って言い張ってもいいと思うんだけどね。僕はそのタイプの演出家じゃない。
――ありがとうございました。

(c)萩原靖
Ort-d.d『肖像 オフィーリア』は2月1日(木)〜4日(日)、池袋の自由学園明日館で上演します。
公演詳細はこちらから
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。