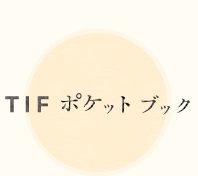3月1日(土) ポスト・パフォーマンス・トーク
トーク出演者:
高山明(Port B)
林立騎(Port B)
谷川道子(東京外国語大学教授/ドイツ文学・現代演劇)
寺尾格(専修大学教授/ドイツ文学・現代演劇)
林:それではただいまよりポスト・パフォーマンス・トークを始めさせていただきたいと思います。今回、翻訳とドラマトゥルクを担当させていただきました林と申します。私の隣におりますのが、Port B構成・演出の高山さんです。
今回は、毎公演後にゲストの方をお招きしてポスト・パフォーマンス・トークをさせていただくことになっていますが、初日の今日は独文関係からお二方、お招きいたしました。谷川道子先生と寺尾格先生です。
私の方から簡単に紹介させていただきますと、谷川先生は東京外国語大学の教授でいらっしゃいます。ベルトルト・ブレヒトやハイナー・ミュラー、ピナ・バウシュに関する多くの翻訳書・研究書をお書きになられています。今回の『雲。家。』の原作者であるエルフリーデ・イェリネクの翻訳書も出版され、多数の論文も執筆されています。
そのお隣が、専修大学教授の寺尾格先生です。寺尾先生は、ボート・シュトラウスやペーター・トゥリーニの翻訳を出版なさっていて、やはり同様にエルフリーデ・イェリネクに関してとてもお詳しく、論文等を執筆なさっています。
今日はエルフリーデ・イェリネクという2004年のノーベル賞を受賞した作家の、戯曲のみならず小説等も広くお読みになっており、ドイツにおける舞台化にもとてもお詳しいお二人をお招きいたしましたので、そういった観点から、今回の公演『雲。家。』について、まずは率直な感想というか第一印象をお話いただければと思います。それでは、谷川先生からいかがでしょうか。
谷川:(舞台一面に広げられている書を見て)まず、舞台に入った時から、これは何の字だろうと思っておりまして、ひょっとしたら毛沢東の書かなと思ったんですが、これは何なのでしょうか?
林:最初、建築足場の中にいるパフォーマーの暁子さんが、下に降りてきてここに入ってきた場面がありますよね。その時に暁子さんが語るテキストが一面に書かれています。
谷川:これは誰が書いたんですか?
林:今回、この東京国際芸術祭に関わっているボランティアの方々がいらっしゃるんですが、その中に増田くんという人がいて、今回いろいろととてもお世話になったのですが、彼のお母様がたまたま師範の資格を持っていらしたんです。いまは教えてはいらっしゃらないんですが、そこをお願いして書いていただいたものです。
谷川:近くで拝見してもとても達筆ですよね。…えーと、率直な感想ということですが、「なるほど、こうきたか」と思いました。このテキストというのは、いわばイェリネク版『ハムレット/マシーン』だと思うんですが、ミュラーの場合の『ハムレット』にあたる種本が、ここではドイツの歴史をめぐる言説、ドイツの歴史において「わたしたち」を求める言説の引用のみなんですね。24のパラグラフだけから成り立っていて、何のドラマ的な仕掛けもないし、誰がどうやって喋っているかもわからない。本当にどうやってこのテキストに対峙するのか、というのが問われるテキストだと思うんです。それに対してPort Bは、「わたしたち」というキーワード、つまり”彼ら”の「わたしたち」に対して、”私たち”の「わたしたち」を探るというかたちで切り返している。その仕掛けに「ああ、なるほど」と思いました。
暁子さんが語るテキストはすべて引用ですよね。普通、ドイツ語を日本語に翻訳する場合には「である」調か「ですます」調かというのがありますが、今回はそれがそのまま「である」調の引用として語られながら、ああいう多言語・多文化状況の日本と、巣鴨なり池袋サンシャインといった非常にローカルでパーソナルな、モノローグの集積としての「わたしたち」を映像で見せながら切り返していく構造になっている。その対比の仕方が非常におもしろかったですね。ですが、そうやって対比させたまま最後までいくかと思うと、最後は暁子さんの語りのみで終わらせる。
寺尾:まずは2点だけ申し上げることにします。1つはイェリネクの作品としてどういうかたちで表現するかというところだと思うんですが、これはいろんなことが言えると思います。つまり、もともとドイツ語ですし、オーストリアという状況の中で出てきたものですから、その点から「これは違うんじゃないか」ということを言っていくときりがない。
僕が一番感心したのは、高山さんの舞台は常にそうですけれども、単純に向こうのものを輸入するのではなくて、日本という状況の中でそれをどう舞台表現していくかということにおいて、ものすごく先鋭的なことをやっていらっしゃる。それが一番よく見えるのが、イェリネクの一番良いところをどう日本語で表現するかというところだと思います。これは実は非常に難しいところで、イェリネクがノーベル文学賞を受賞したのは皆さんご存知だと思うんですけれども、その場合の一番重要なポイントは、イェリネクの持っている言語の音楽性というようなものが非常に高く評価されたというのがあるんです。これをそのまま日本語にしても、その良さは出ない。そこで文句を言い出すときりがないんですが、その言語の音楽性を、「わたしたち」というテーマのものを、たった一人の暁子さんのモノローグで、それを日本語の持つ音楽性としてどういうかたちに転換できるかというところで、非常に見事にやっていらっしゃると思います。
イェリネク論としてみると、もちろんドイツ語の持っている、もともとのテキストの「わたしたちは、わたしたちの家にいる」というのは、日本語の訳とは文脈のニュアンスが全然違うんですよね。しかし、そういうところで文句を言ってもあまり意味がない。イェリネクの持っている言葉の音楽的な表現というものを、非常に上手く消化して舞台化しているというところは、僕は非常に感心しました。
それからもう1点は、高山さんの舞台は一方でドイツの戯曲があり、前回はアイナー・シュレーフの『ニーチェ』をおやりになりましたが、あのあたりのものを非常にうまく利用されているというのと、もうひとつ高山さんがドイツとは関係なく、高島平だとかの<都市の記憶シリーズ>というものをおやりになっていますが、今回の舞台でもサンシャインを出されていて、「これは上手い!」と思いました。たぶん、あのあたりでこのイェリネクをどう日本で表現していくかということの核が、ご自分の中で見えてきたんじゃないかと思います。その意味でも、高山さんがこれまでやってきた2つの流れがここで交差して、独特な高山ワールドになっていると思います。以上、褒めました。けなすのは今度個人的にします(笑)。
サンシャインビルの映像が墓場の向こうに見えるかたちで撮られていましたが、あれを見るとサンシャインそのものが墓に見えますね。今回はあまり難解にやらないで、ちゃんと墓場を見せて、その向こうにサンシャインを見せるという、誰が見てもわかる作りになっていますね。この戯曲のテーマそのものが、ドイツのナショナリズムが持っている負のものに関わっていると思うので、そこを上手く絡み合わせていると思います。
谷川:先程「なるほど」と言いましたが、それはドイツのバックグランドを持って、日本に帰国された高山さんが、2000年代の日本という現実の中で、それこそ何もないところからひとつひとつ探っていて、スタイルを作っていっていますよね。私たちは最初からずっとPort Bの活動を見ているんですけれども、高島平の団地の中からボルヘス的な空間を立ち上げていくプロセスだとか、一人一人がイヤホンで案内されながら巣鴨の地蔵通りをひとつひとつ発見していく『一方通行路』だとか、つまりパーソナルでローカルで、なおかつこれが演劇として成立するという空間を探っている。それとドイツのテキストとが、やっと交差したんじゃないかなと思います。そういう意味で、イェリネクというテキストを知っていて、Port Bの活動を知っている人間からすると、非常に納得する舞台でした。

(C)松嶋浩平
林:このままだと高山さんが喋らないで終わってしまうので、折角ですから高山さんがドイツであるとかボルヘスのものを日本でやるということに関して、話していただけますか。
高山:素材は別に何でもいいところがあるんですね。ドイツの戯曲ばかりをやるつもりもあまりないんですが、自分とあまり接点がないようなテキストをやる方が好きなのかもしれません。僕はどちらかというと、物語とかおとぎ話の方が好きなタイプなんです。自分で戯曲を書いていたりもして、自分で言うのも何ですがまあまあの出来だったんじゃないかなと思います。物語を作るんだったら、一晩で百本は作れるなというぐらい出来るつもりではいるんですけれども、そういうのをやると結構おもしろくなかったりするんですね。僕自身もおもしろくないし、舞台もおもしろくない。それはお客さんとの関係でもわりと言えることだと思います。
さっき「わかりやすい」と仰っていただきましたけれども、あの(サンシャインの)映像を撮ったのは宇賀神さんという方で、編集は三行くんなんですけれども、「何かお墓とサンシャインがクロスするような映像を撮ってきて」と僕が言うと、勝手に行ってくれて勝手に撮ってくれるんですね。それで「こんなの撮ってきた」といって持って帰ってきてくれるんですが、僕は自分でやるとすると、もっと地味な、お墓とわからないようなものを使っちゃうタイプなんですね。それが、彼らがやることによってフレームもしっかりするし、イメージとしてもはっきりするようなものが撮れたりする。
自分とテキストの間に溝があればあるほど、自分の方がかきまわされる感覚がありますね。それは人と共有する作業の場合でもそうで、人に何かやってもらって、それが返ってくると、当然自分がイメージしたものとずれる。あとお客さんに対しても、たとえば「ドイツ人!ドイツ人!ドイツ人!」という言葉が来た後に、いきなりサンシャイン60が映ったりしますね。それから「ゲルマン帝国が現れる」という言葉がありましたが、あれを言っているのは皆アジアからの留学生だったりするんですね。だから、舞台の上でも常に溝を作りたいという思いがあって、僕もその溝にはまっていきたいと思います。
寺尾:たぶん、溝というかぶつかり合いだと思うんですけども、ちょっとどうしても言いたいことがありまして、タイトルのことなんです。この「汝、気にすることなかれ」という谷川さんが訳していらっしゃる本がありまして、大変にいいイェリネクの戯曲集なんですが、こちらにも”Wolken. Heim.”のタイトルについてきちっと訳しておりますでお読みいただければと思うんですが…。
それで、いま高山さんが仰ったことを私なりに引っ張ってきますと、この戯曲の原題”Wolken. Heim.”を日本語に直訳すると確かに『雲。家。』となるんですが、日本語で「雲」というと、それは白い雲で、後ろに青い空があるというイメージじゃないかと思います。そして『雲。家。』となると、何となく「雲の家」とか、昔、石井桃子さんの「ノンちゃん雲にのる」という本があったりしましたけれども、何かほわんとした雰囲気があると思うんです。だけどWolkenというドイツ語の持っているイメージは全然違うんですね。もちろん白い雲というのもあるんですが、圧倒的に黒い雲といいますか、暗雲なんです。もしドイツ語をおやりになっている方がいましたら独和辞書を引いていただきたいと思うんですが、後ろ側に嵐を持っている黒雲で、その嵐とのつながりを持った雲がこう覆いかぶさってくるような、そういうイメージなんですね。それがWolkenの基本の意味です。HeimはHomeですから、これは心温まるポジティブなイメージですね。しかしWolkenの後にその言葉が続くわけで、明らかにこの2つの言葉のイメージはぶつかり合っています。
谷川:それから、このタイトルはWolkenkuckucksheimという、アリストパネスの喜劇『雲』と『鳥』に由来する「雲の上のカッコウの家」からきています。『雲』というのは雲の上に桃源郷を作ってソクラテスに喋ってもらうというもので、『鳥』というのは、現実のものすごく荒れた場所を逃れて雲の上に家を作ろうという喜劇なんですけれども、『雲。家。』というのは、もともとWolkenとHeimの間にあった、Kuckuckつまりカッコウというのが抜けているんです。カッコウというのは他人の巣の中に自分の卵を産んで、そして育ててもらう鳥です。だからカッコウというのは「ありがたくない贈り物」という意味でもありますし、Wolkenkuckucksheimという言葉自体がものすごく意味深な言葉なんですね。カッコウというのはつまり他人の中に入れられた自分であり、「わたしたち」と言う人に対する他者であったり、ドイツ共同体の中でもオーストリアであったりとか、カッコウという言葉を抜いたことで、いろんなイメージが考えられる。ホームとは何なのか、他人の巣の中のカッコウとは何なのか、それは他者と自分との間の、空白の部分を意味してるんだと思うんですけれどもね。それをたぶん高山さんたちは、私たちにとって「わたしたち」とは何か、他者とは何か、ホームとは何か、ということに変えられたと思うんです。
どうしてこういう形になったのかということをお聞きしたいなと思うんですが、今回のテキストは林さんが全部翻訳されたんですよね。こういうテキスト構成にされた理由についてお話していただけますか。全部が全部イェリネクではないと思うんですが。
林:暁子さんの語りはすべてイェリネクのテキストですが、一箇所だけ、映像に縦の字幕が映るところがあります。そこだけがイェリネクのテキストではありません。
ざっとテキストを翻訳したプロセスについてお話しますと、このイェリネクのテキスト『雲。家。』は、ほとんどすべてがヘーゲルやヘルダーリン、フィヒテ、ハイデガーといった人たちの文章の引用だったり、その中の数語を変えて使っているわけですね。それをどうやって訳すかという時に、幸運なことにマルガレーテ・コーレンバッハというドイツの学者の論文を見つけまして、それはこのページにはここからの引用があるということをほとんど調べてくださっている労作だったんですね。それが最初に見つかったので、ヘルダーリンとかヘーゲルの、もとのテキストのコピーをすべて用意して、そのテキストを見ながら翻訳しようと思ったんです。そうやって参照しながら、全体の中でどういう意味を持っているのかを理解して訳そうと思ったんですが、それがどうにもうまくいかなかったんです。
それでどうしたかというと、たとえばヘルダーリンの50行なり100行なりの詩から一行が引用されているとしたら、その50行なり100行なりを全部訳す。そして自己引用するというかたちで、『雲。家。』というテキストを翻訳していきました。つまり、ヘルダーリンの詩で引用されているものは、その引用元の全体もすべて翻訳したんですね。そうすると、本文そのものはA4で14枚だったんですが、註が120枚くらいになりました。そういうかたちでやらないと全く歯が立たなかったんですね。このあたりは上手く説明できないんですが、翻訳という作業を便利にやろうとしたら立ち行かないんです。引用されている詩の全体と付き合って、そこから自己引用するというかたちしか思い浮かばなかったんです。だから少し時間がかかってしまいました。
寺尾:そのあたりが高山さんが苦労されているところだと思うんですけど、いわゆるオーソドックスなドラマであれば、さまざまな引用みたいなものは無視しても、ドラマのところだけを追っていけば我々はわかるわけですよ。ところが、このテキストはほぼ全面引用で、前半はヘルダーリンが中心なんですが、真ん中あたりからフィヒテとかハイデガーとか、特に赤軍の、70年代のドイツテロリズムの台詞がぼんぼん出てくる。そういうところにあんまりこだわっちゃうと、舞台の上ではわからないし、たぶんドイツでもそんなにわからないと思うんですね。ましてや日本に持ってきたら全然通じるわけがないんです。だからそのあたりは、何となく雰囲気でわかればいいかなと思います。本来はものすごく政治的なテキストで、ドイツのナショナリズムというものがどんどん作られていく時期、要するにフィヒテが「ドイツ国民に告ぐ!わがドイツ人よ!」とかやっていた頃のことですよね。
谷川:ドイツの統一国家というのはものすごく遅れて、19世紀の末になってできるわけですよね。ヘーゲルだとかヘルダーリンもみんなそうなんですけど、だからこそ、国家への思いがどんどんできていく。
寺尾:だから今見ると、そのままだと結構危ないテキストが出てくるんですが、そこにこだわってもしょうがないと思います。もちろん、こだわらざるを得ないところもあるんですが、そこを前面に出して政治的なテキストみたいにすると、たぶん日本では通じないと思われたんでしょうね。だからむしろこのテキストの持っている政治的なものと音楽的もののうち、むしろ音楽的なものを前に持ってきて、後ろ側に政治的なものをさりげなくほのめかすというかたちにしたんだと思います。いわゆるイェリネク論として言うならば、本来逆だとは思うんですが、それをひっくり返して紗の向こう側は全体が骨組みみたいになっていて、一種の牢獄的なイメージで、そしてこちら側があるという形にしている。これは僕の深読みかもしれないんですけれど。
だからイェリネクのテキストが持っている意味というものを、ただ右から左に翻訳するということではなくて、それを舞台の上で高山さんが上手く処理している。自分のものとして捉えて、表現しているというところが私は感心いたしました。
谷川:私のところにも、ヘルダーリンの訳が付いた、ものすごい量のテキストが送られてきたんですが、あの膨大な量を潔く切って、この舞台を作られたというその潔さに感心しました。だからイェリネクをそこまで突き詰めた上で、それを放り出しているんですね。
寺尾:そうですね。だから見ていると、「あ、いまヘーゲルだ、いまフィヒテだ、いまドイツ赤軍だ」というのがわかるんですが、そういうところを全面に出さずにさらさらとやっていらっしゃると思うんですが…そんなことはないですか?
高山:やっぱりよくわからないところがずいぶん多かったんですね。これが赤軍の話だということも、林さんが調べてくれてわかったんですが、つながりかたが全然わからない。僕らの場合は、プロセスでどういうことが起きているのかなということにわりと注意するんですよ。そこにいい宝が転がっていないかな、という感じで。
林さんから翻訳の本文14枚と註120枚が送られた時、これを一冊の本にした場合、どういうかたちになるのかなと考えたんですね。普通の本だったら、註は脚注みたいなかたちで下に付けますが、14枚の本文で120ページの註ってアンバランスですよね。具体的な内容よりも形式として、このテキストで扱われているようなことって、マラルメが「世界は一冊の書物に到達する」と言いましたが、「これはどう考えても一冊じゃないな」という感覚がすごくあるんですね。
寺尾:たぶんドイツ人であれば、たとえばヘルダーリンの文章にフィヒテが入ると明らかに調子が違いますから、そこはある程度雰囲気としてはわかるんじゃないかなと思うんです。でもそれを翻訳で出すのはたぶん不可能に近いですよね。だからそこはさらっとやっていいと思います。お客さんが日本語で舞台を観たときに、「あれ、さっきと調子が違うな」というところを、実際どのぐらい感じてるのかなというのは、ちょっと知りたいような気もしますね。

(C)松嶋浩平
谷川:ドイツでの上演を私はビデオで見たことがあるんですが、ヨッシ・ヴィーラーの演出はこれを言葉の塹壕と捉えて、塹壕の中に5人の女性を置いて、その女性たちがテキストを分読するんですね。ところどころにドイツの民謡みたいなものを散りばめながら。まさにコロスのような感じでした。
寺尾:言葉による合唱ですね。谷川さんもドイツでイェリネクの上演はずいぶんご覧になっていると思いますが、イェリネクの作品というのは概ねコロスなんですね。合唱系統で、アンサンブルでやっていくのが多い。だから高山さんがこの「わたしたち」というテキストを、あえてたった1人に語らせるというそのオリジナリティがすごいと思います。
谷川:シャウビューネの女優によるモノローグのCDがあるんですが、一切ヘルダーリンやヘーゲルを感じさせずに語っていて、日常の語りとして恐ろしいほどノーマルに聞こえてくるというものがあるんですが、そのコロスとソロという対極の中にイェリネクがある。今日の場合、ソロとコロスのいろんな段階を映像も含めて見せてくれたので、それが非常におもしろかったですね。こちらにソロを置いて、向こうにコロスが出てきたりですとか、しかも声の演劇が映像の演劇として転換されてくるというところがとてもおもしろかったです。
寺尾:しかも、舞台にテキストを置いて、その上に乗っかってテキストを語るという、言葉と舞台というのをどういう具合にうまくやっていくのか。いま現代演劇というと、どちらかというと言語に対してかなりシビアに見ていて、むしろ身体という方向に行ったりするパターンが非常に多いんですが、そうじゃなくて、言葉が持っている音楽性を前面に出すという、演劇じゃないと出来ない表現というものを、高山さんは一貫してずっと試みている。これがこういう舞台を作るひとつのルーツになっているんじゃないかなと思います。これは意図的なんでしょうか?
高山:結構そこはこだわろうかと思っているところです。僕らの舞台は「身体性がない」とよく言われるんですが、僕は声も身体だと思っています。僕はある演出家の稽古を見させてもらったことがあるんですが、その演出家は人と人とが話しているような感じに見えるとすごく怒るんですよ。「そんな風にやるな」と言うんです。人と人とが話しているんじゃない、声と声とが話しているんだ、と言って修正していくんです。その演出家というのはグリューバーなんですが、それを聞いたときにすごくはっとしたんです。最近は「退屈」とか言われて人気が落ちているんだけども、僕は彼の作る舞台がすごく好きだし、ああいう舞台みたいなものを、動かないんだけども声が動く、声によって空間が変わるということをやりたいと思っています。
なぜ今回の舞台をこういう形でやりたいと思ったかというもうひとつの理由が、ヨッシ・ヴィーラーなんですね。ヨッシの舞台をビデオで観たんですが、やっぱり衝撃的だったんです。こういうモノローグをいろんな人物に振り分けているんですが、振り分けて音楽的に作るだけだったら、そんなに難しい作業じゃないと僕は思うんです。だけど彼の場合は、その言葉が全部内面化されて、人物のものになっているんですね。これを自分ができるかと考えて、たぶん出来ないと思ったんです。ああいう傑作を作った人と同じことをやってもしょうがないし、実際出来ない。だったら何があるかなと考えました。
そうすると、たとえばグリューバーの「声の演劇」のように、声で何かを表現する。たとえば1人であっても、「わたしたち」という主語が単純なモノローグに聞こえたりだとか、あるいはここにある洋服たちが皆で発している声に聞こえたりだとかが出来るんじゃないかと思いました。ヨッシが分裂させたものを、1人の人物にぜんぶ詰め込んで、お客さんの力によって、ある時は5人に見えたり、ある時はたった1人に見えて「わたしたち」という言葉が空しく響いたりだとか、そういう形で、ヨッシの舞台ではない、かすかな隙間みたいなものを違った形で舞台化できるんじゃないかなと思ったんですね。
寺尾:ここらへんは、やっぱり暁子さんが「わたし・たち」というように、通常の喋り方を異化するかたちで、独特な語りでやられていますよね。あれにだいぶ負っているところがありますね。暁子さんの語りは聞いているとちょっといい気分になるんですね。でも語られている内容のほうは、結構シビアな、どきっとするようなことを言っている。しかしそれをある種漂うように語っている、その2つのずれみたいなものがある。いろんなところにずれというか対立があって、イェリネクのテキストそのものがいろんな意味を持っていて、非常に素朴にタイトルを見たときのイメージと、もうちょっと知識のある人たちのイメージは違うし、いろんな深読みができる。ということは逆に舞台に対しても「これはこういう舞台なのである」と絶対に言いきれない。見ている人がそれぞれに感じる、そういうものを作っていく舞台として、この日本で具体的に作られているなと僕は思いますし、そういう意味で非常にいい舞台であると、僕は個人的には高く高く評価しています。
林:話は尽きないんですが、そろそろ時間になってきました。今回このアフタートークでは、質疑応答の時間というのは設けておりません。その代わり、このトークが終わった後に、裏手のロビーでお飲み物と簡単なつまみを用意させていただきました。そちらに、僕らをはじめとしたPort Bメンバーが当分ふらふらしていますし、先生方もまだ残っていただけるとおもいますので、ぜひそちらでラフなかたちで歓談しながら、皆様にも楽しんでいただければと思いますので、ここでポスト・パフォーマンス・トークは終わらせていただきます。今日はどうもありがとうございました。