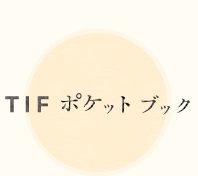3月2日(金) ポスト・パフォーマンス・トーク
トーク出演者:
高山明(Port B)
林立騎(Port B)
井上達夫(Port B)
熊倉敬聡(慶応義塾大学教授/文化実践論)
林:本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。それではポスト・パフォーマンス・トークを始めさせていただきたいと思います。まずPort Bのメンバーから紹介いたしますと、私は今回翻訳とドラマトゥルクを担当させていただきました林と申します。一番奥がPort B構成・演出の高山さんです。そして今日から毎公演後は、私と高山さんだけではなく、Port Bの公演に毎回参加してもらっているコアメンバーから1人ないしは2人にこのトークに参加してもらうのですが、今日来てもらったのは、普段は毎回パフォーマーとして活躍されていて、今回は技術監督として参加されている井上達夫さんです。そして、今回のトークのゲストとしてお招きしたのは熊倉敬聡さんです。
熊倉さんは慶応大学教授でいらっしゃいまして、かつてはマラルメを中心としたフランス文学研究、マラルメの社会思想、経済思想の研究から出発なさった後、学問、あるいは大学における知のあり方に対する批判的考察をもとに、芸術と社会であるとか、芸術と教育のつながりについて、文化実践論というかたちで活動なさっています。このにしすがも創造舎の中に入っている、NPO法人「芸術家と子どもたち」の理事でもいらっしゃいます。その熊倉さんをお迎えして、今日の公演をご覧になった率直な感想と、Port Bあるいは高山さんにご質問がありましたらお話していただきたいと思います。
熊倉:時間もあまりないと思いますので、ごく率直に申し上げたいと思いますが、…圧倒されました。いろんなことを考えさせられましたね。先程ご紹介していただきましたように、私は20年前までマラルメというフランスの19世紀末に活動した詩人の研究をしていたんですが、マラルメを代表とした19世紀のある種の思想家や芸術家たちが共通して持っていたテーマと、今回のテキストは共鳴するところがすごく多いですね。
皆さんご存知かもしれませんが、今回元になっているテキストは、18世紀、19世紀のドイツの、ヘルダーリンやヘーゲル、フィヒテなどの言葉が引用されて紡がれているんですが、たとえば「種族」とか「わたしたち」とか「大地」とかの言葉は、僕が研究していたマラルメの作品にもたくさん出てきたり、同様な探求をしていた詩人の詩にも結構出てくるんですね。
このテキストもそうなんですが、おもしろいのが、2つの意味があるということです。たとえば、「種族」といった場合も、文字通りの「ドイツ民族」という種族という場合と、メタファーとしての種族という場合があります。たとえば詩人であれば言語を使って芸術活動をするわけですが、普通は言語というのはあるテーマだとか、ある世界を表象するために使うわけですね。19世紀のある種の芸術家や思想家というのは、そういうためではなくて、言語が言語自体を問題にしていくような文学作品を書いていく人が多かったわけです。そうすると、言語が言語を問題にするわけですので、言語が分裂して解体していってしまうわけです。同時に、言語を操っている人間の自我も分裂して解体していくし、言語が表象していた世界も分裂し解体していく。最終的にそれを突き詰めていくと、今まで言語とか自我を作っていた、目に見えない構造みたいなものが見えてくるわけです。それをマラルメという人は、音楽という比喩を使って言ったんですが、ある種別の言い方をすると、存在が存在に対して開いていくということを深化していった結果なんですね。そういう風に、存在が存在を深めていって、存在に対して内在的に目覚めている状態、そういう自分たちを「わたしたち」と言いまして、その「わたしたち」というのはひとつの精神的な種族であり、場合によっては選ばれた者たちである、という言い方をするんです。でもそれは比喩であって、別にそれが直接植民地主義やナショナリズムに結びつくわけではないんです。
たとえばマラルメを代表とするフランスの場合は、「種族」というのはあくまでメタファーであって、それが直接政治的な、フランス民族の謳歌につながるとか、そういうことにはならないんですね。ところが不思議なことに、ドイツである種同様な探求をしていたヘルダーリンにしてもヘーゲルにしても、なぜかその「種族」という言葉が、文字通りの「ドイツ民族」という意味を持ってしまうんです。
今回のこの作品を観ても、メタファーとしての「種族」と、文字通りの「ドイツ民族」という、2つの意味の二重構造になっているわけですが、それをこの作品では使っておられるわけで、そこは非常に考えさせられました。字義通りに使うというのは、たとえば極端な例でいえばナチズムですよね。字義通りに「種族」という言葉を使って、他者を支配する道具として思想を文学を使ったわけです。
今回のPort Bの場合は、ある種それを字義通りに捉えているわけですが、でもそれはナチズムをやりたいわけではなくて、日本の今の政治主張を代表するようなある種のナショナリズムを批判する道具として使っているところがあるでしょうし、彼らの政治意識を明らかにするために使っている。そこは全然使い方が違うと思ったので、そこは非常におもしろいと思いました。

(C)松嶋浩平
林:今回のテキストの場合、テキストの中にドイツとかゲルマン帝国といった言葉があからさまに出てきます。そういったテキストを日本という、つまりその言語が書かれたわけではない場所でどうやってやるかという問題があるわけですが、先程皆さんがご覧になったように、今回はそうした言葉をそのまま使っています。ではどうしてそういう風にしたのかということを、高山さんの方からお話いただけますか。
高山:今回のテキストというか、林さんの翻訳をもらった時の印象からお話するのが一番いいかなと思います。これは難しいな、どうやって上演しようかなとまず考えました。もともと、読んですぐ舞台のイメージがわくというタイプでもないですし、逆にそういうのはやらないようにしているんですが。
もともと、ヨッシ・ヴィーラーという演出家から、この作品の上演は外国語では絶対に無理だと言われたんですね。だから「だったらやろうかな」と思ったんですが、実際読んでみたら難しくて「やっぱりできないな」と思ったんですけれども、じゃあたとえば日本語でこれをやるとしたら、どういう利点があるだろうと考えたときに、「わたしたち」という言葉はドイツ語だったら「wir」ですが、日本語だと「わたしたち」とか「我々」とか「僕ら」とかいっぱいあると思うんです。そういう風に分けてやろうかなと思いました。
だけど、ヨッシ・ヴィーラーの舞台との比較で言うと、彼の舞台では5人の女性が出てきて、ある時は一体になったり、ある時はその中で闘争が始まって分裂したりだとかを、一人一人の人物に分けてやっているんです。もし僕が、言葉を「我々」とか「僕ら」とか「わたしたち」という風に分けてしまうと、登場人物が1人であっても、あんまりヨッシのやっていることと変わらないなと考えて、じゃあ最初から最後まで「わたしたち」というひとつの言葉で通そうと思いました。その色合いとか、本当の中身が変わるのは、お客さんにやっていただけたらと考えました。「ドイツ」という言葉も、「日本」に変えるよりはそのままにして、言葉の中にも溝があるし、テキストの意味内容にも溝があるようなかたちを一貫して通した方がいいなと思ったんです。その溝はお客さんの想像力で埋めてもらう。その方が、今この戯曲を日本でやる意味があるんじゃないかなと考えました。
林:今回の舞台では、テキスト自体が観客に提示するような溝はそのまま残しつつも、アジアからの留学生だとか、サンシャイン60だとかが、映像として急に入り込んでくるわけですよね。そういうものをどう見られたのか、まずは熊倉さんからお話していただけないでしょうか。
熊倉:今回のトークをお引き受けするにあたって、まず最初にいただいたのがイェリネクのテキストだったんですが、結構な枚数で、プリントアウトするのが大変でした。それをまず読んだときに、本当にこんな戯曲を日本でやって、それが理解されるんだろうかと思いました。どうやってこんなものを芝居にするんだろうと思ったんですが、おもしろいと思うのは、Port Bは池袋のサンシャイン60について若者にインタビューしたりですとかアジアからの留学生たちと話を聞いたりして、それとの関係でこのテキストを考えていくという発想なんですよね。それがすごくおもしろいなと思いました。
この間の巣鴨地蔵通り商店街の『一方通行路』もそうですが、ある種非常に知的な操作がいるテキストを、ものすごく具体的な現実のところで読み換えた上で、舞台にしていくというところが、普通の劇団ではあり得ないですよね。そこがおもしろいですよね。
高山:『一方通行路』は結構、極端な形で出たと思うんですけれども、わりといたずらみたいなものが好きなんです。そういう発想で考えると、このテキストと一番直接的に結びつくのは靖国だと思うんですが、それだとあまりおもしろくないというか、苦労が足りないと思ったんですね。もうちょっとおもしろいものがないかなと考えていたんですが、サンシャイン60というものに僕は昔からすごく興味があったんです。僕は埼玉出身で、まだ小学校の頃、学校のベランダからあのビルが見えたんですね。「あれが日本一のビルだ」と思いながら見ていました。
熊倉:一時期は「東洋一」と言われていましたよね。
高山:そうでしたよね。たとえばああいう巣鴨プリズンという、戦犯の人たちが処刑された場所というのは、もしドイツだったら絶対に残すと思うんです。あるいは記念碑みたいなものを作るんじゃないかなと思ったんです。それがよく調べていったら、昭和33年まであそこはアメリカの土地で、巣鴨プリズンという形で保持されていたのが、いきなり囚人付きで日本に返却された。当時はアメリカの民主主義が広まっていった中で、戦犯の人たちの話を読むと、どこにも寄る辺がないんですね。死刑になる時に、「やっと大地が歩けた」とすごく感激して死んでいったという話もありました。そこにサンシャインという、日本一、あるいは東洋一の建物を建てた。この戯曲には「大地」という言葉がたくさん出てくるんですが、そこと結びつけたらおもしろいなと思ったんです。ある種のいたずらと共通するところがありますね。
熊倉:僕もダッハウの強制収容所に行ったことがあります。サンシャインと同じくらいの敷地で強制収容所の建物はだいぶ取り払われていましたね。ちょうど僕が行ったときはすごく天気のいい日で、もしかしたら同じいい天気の日を、ここに収容されていたユダヤ人たちも同様に見ていたんだなと考えるとすごく鳥肌が立ちましたね。でも、ドイツの場合はそういうものをあえて残すんですね。だけど日本の場合はあえて残さずに、西武の創業者の方が、もしかしたら意図的にあそこにサンシャインを建てたのかもしれない。民族性といったらおかしいのかもしれないですけれど、日本の戦争への対し方と、ドイツの戦争への対し方というのは対極的ですよね。
高山:名前も結構過激だと思っているんです。闇の部分を闇として残すのではなく、「サンシャイン」、つまり光り輝くという言葉で闇を消してしまう。僕は演劇でも出来るだけ、闇の部分みたいなものを闇としてそっくりそのまま出せばいいじゃないかと思うんです。化粧して、光り輝くものにするのは、今回はできるだけ避けようと思いました。
熊倉:サンシャインを、あえて墓に読み換えているという感じでしたね。
高山:不思議なもので、ずっと見ていると本当に墓石に見えてくるんです。稽古のためにこちらに通っている間、ずっとあちらの方角にあるサンシャインを見ていましたが、だんだん墓石にしか見えなくなってきて、気持ち悪くなってしまいました。

『Re:Re:Re:place 〜隅田川と古隅田川の行方(不明)〜』(c)Yuichiro Tanaka
林:Port Bの公演を2年以上観ていらっしゃる方はご存知だと思うんですが、昔は「都市の肖像シリーズ」という名前で、高島平の団地であるとか、隅田川をフィールドワークして作った作品だとか、巣鴨地蔵通りをフィールドワークして実際にお客さんにも歩いてもらう『一方通行路』という公演がありました。今回も現実の都市が舞台に入ってきています。いい機会なのでここでお聞きしたいと思うんですが、僕は田舎の出身でして、そこは戦争の影響もなくて、古いままに残っているところなんですね。でも関東や東京はそうではない。高山さんは埼玉の出身ですし、井上さんは東京生まれですよね。だから隅田川や高島平、池袋を調べるというときに、自分たちが生活してきた場所の地下を潜るような、過去を探るような感覚があると思うんです。それは僕が「東京って昔はこうだったんだ」と思うこととずいぶん違うような気がします。そういった調べものをすることについてどう思っていらっしゃるか、井上さんからお話していただけますか。
井上:『Re:Re:Re:place 〜隅田川と古隅田川の行方(不明)〜』という作品を以前やりましたが、実際僕はあの辺りの出身なんですね。皆がいろいろ調べてくると、何だか自分の過去が暴かれていくような感じがして、最初は結構嫌でしたね(笑)。でもだんだん楽しくなってくるんですよね。隅田川について調べているうちに、なぜか海人族とか、そんなところまで話が広がっていく。フィールドワークといってもその土地についてだけの資料を集めていくわけではないんですね。ものすごい量の資料を毎回集めるわけですが、でも舞台で使うのは4、5ページ分だったりして、切り捨てる部分がすごく多いですよね。だから傍から見ると無駄に見えるのかもしれないんですけれども、でもやっている本人たちにとっては、舞台に立って、語るときに、「どれだけの背景を背負っているかわかるか」という自負みたいなものはありますね。それを稽古というのかわからないんですが、毎回必ず膨大な資料を集めてかきまわされて、そこからエッセンスを自分たちで作り出すというかたちで作業を進めていますね。
高山:正直に言いますと、とりあえず最初の段階で何をやるべきかわからないというのがあるんです。ですが、その時に何をやるかというのは結構重要な問題じゃないかなと僕は思っています。これがたとえば、すっごく売れている劇団だったらそんな時間はないと思うんですが、僕らにはわりと時間的な余裕もある。そうすると、最初に形を求められるということがないんですね。僕は、それはすごくありがたいことだと思っています。いつも形は最後の最後まで決めたくないと思っています。だから、最初にいっぱい資料を集めてこちらがかき回されて、何かが出てくるのを待つ必要があるんですが、ただ待っていてもあまり意味はないので、とにかく何かやってみる。そうすると、そのうち自分が考えるでもなく、素材が形を与えてくれるというか、その中間ぐらいに出てくる瞬間みたいなものを掴めたら、それはいい舞台になるんじゃないかと僕は思います。
林:今回もプランは何度も変更していて、最終的にこういう舞台になると決まったのはすごく遅かったんですけれども、資料を集めてこういう舞台にしようと言ったからって、コンピューターのプログラミングじゃないんだから自動的にこういうものが出てくるわけじゃないですよね。たとえばこういう映像が欲しいといったところで、高山さんが撮れるわけでもないので、Port Bの映像班が素晴らしいフレーミングで撮ってくるわけです。そして今回、皆さんがこの劇場に入った時からびっくりしてもらえたかと思うんですが、この一面に敷かれてある布に書かれてあるのは、上演の中で暁子さんが喋っているテキストの一部です。これも、地面に書を一面に書いた布が欲しいと高山さんが言い出したんですね。とはいえ高山さんが書けるわけでもないのでいろいろ探し回りましたが、今日この客席の中にいらっしゃる増田隆子さんという方がこの書をすべてお書きになられました。6時間くらいかけて、その6時間の間全く何も飲まずに書かれていました。僕はずっとついて見させていただいたんですが、素晴らしいパフォーマンスでした。そしてこの布を、また別の方に丸1日かけてミシンで縫っていただきました。コンセプトがあればすべてが生まれるわけではないので、ひとつひとつのものがいろんな技術者といろんな方々の好意で出来ています。
熊倉:この舞台はわりと短期間で集中的に作られたと先程仰っていたんですが、ミーティングなどに結構時間をかけられるんでしょうか。
高山:僕は稽古場で話し合いということ自体、あまり好きではないんですね。できれば喫茶店ですとか、飲みながら話したいですね。ほとんどお喋りになっているんですが。最初に話し合いをして、何となくみんなの間で共通理解みたいなものができると、たとえば「こういう映像が欲しいんだけど」みたいなことを行ってメンバーに勝手に撮ってきてもらっても、自分の狙いから外れていなくて、しかも自分が思っていたものよりも良いものが出来てくるという、奇跡みたいなことがわりと起きるんですね。
熊倉:ある時期のダムタイプの作り方なんかも、演劇出身の人ばかりではなくて、建築やっていたりとか、写真やっていたりとか、いろんなジャンルの人がいて、それぞれ自分の得意技をお互いに出し合っていくんですが、そういう手法は似ているなと思います。
高山:そこはちょっと意識するところがあります。彼らはすごく貴重な活動している人たちだと思うんですが、もうひとつ増やしたいなと思うのが、たとえば今回はこういう風に客席があって舞台があるというものになっていますが、それ以外の活動というのもすごく重要だと思うんです。そういうことをこれからやっていきたいですね。
熊倉:ダムタイプも90年代に、京都という都市空間の中で、今でこそありふれていますけれどオルタナティブな活動を始めたりですとか、アートセンター的な活動を始めたりですとか、演劇活動とは別に文化の調整装置を作っていたわけですよね。Port Bとして具体的に目指す活動というのはあるんでしょうか。
高山:『一方通行路』では少しそういうところに触れた気がしてるんですが、2008年の3月くらいに、今回取り上げたサンシャイン60をもっと徹底してやりたいなと思っています。サンシャイン60の周りを60箇所くらいツアーするようなものが出来たらいいなと思っています。
林:今回のポスト・パフォーマンス・トークでは質疑応答の時間はご用意しておりません。客席裏手のロビーにビールやワイン、簡単なおつまみをご用意しておりまして、そこで私たちPort Bのメンバーや熊倉先生も当分ふらふらしています。感想や質問など聞かせていただける方は、ぜひもう少しゆっくりしていただいて、そこでお話していっていただきたいと思います。
熊倉:最後に宣伝をしていいでしょうか?
この東京国際芸術祭の公演のひとつなんですが、今度チェルフィッチュという劇団の演出家・岡田利規と一緒に、ドラマトゥルクという役割でサミュエル・ベケットのラジオ・ドラマ『カスカンド』という作品をやります。昨日から稽古をやり始めて、自分で言うのも何ですがなかなかおもしろい作品になりそうなので、ぜひお越しいただければと思います。
林:というわけで、ひとまずポスト・パフォーマンス・トークは終了とさせていただきます。この続きはロビーでやりましょう。今日は本当にありがとうございました。