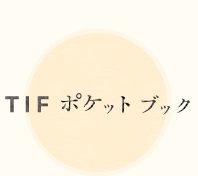3月3日(土) 夜公演 ポスト・パフォーマンス・トーク
トーク出演者
高山明(Port B)
林立騎(Port B)
宇賀神雅裕(Port B)
三行英登(Port B)
藤原敏史(映画監督)
林:本日はご来場いただきましてどうもありがとうございました。これからポスト・パフォーマンス・トークを始めさせていただきます。今回はPort Bから4名が参加し、ゲストの方を1名お招きしたのですが、まずはPort Bの側から紹介をさせていただきます。私は今回、テキストの翻訳と、ドラマトゥルクとして制作上の諸々を担当させていただいた林と申します。一番奥がPort B構成・演出の高山さんです。本日のゲストは映画監督の藤原さんということで、Port Bからも、映像に関わっているメンバーに来てもらいました。今回は映像を多用した舞台でしたが、そうした映像をひとつひとつ、手仕事的に作ってくれているお二人です。
まずこちらが宇賀神雅裕さんです。宇賀神さんは、演劇と関わるようなお仕事はPort Bだけで、普段はテレビや映画の方で映像の制作・編集をなさっています。それから、高山さんの隣が三行英登さんです。三行さんは映像作家であり、またグラフィック・デザイナーとしての活動もなさっていて、僕らのチラシや当日パンフレットなどのデザインをすべてやってくださっています。また、今回の映像オペレーションなどもすべてして下さっています。
そして今日お招きしたゲストが藤原敏史さんです。藤原さんは映画批評から活動を始められ、バスター・キートンの自伝を翻訳されたり、また映画に関する共編著も多数刊行なさっています。そして2002年から映画監督業に進出されました。2006年には初の劇映画「ぼくらはもう帰れない」がベルリン映画祭で上映され、新進気鋭の映画監督として注目を集めていらっしゃいます。
まずは今日初めて舞台をご覧になった藤原さんに、率直な感想とご質問などがあればお話いただきたいと思います。
藤原:実は大変に恐縮なんですが、ここにいる観客の皆さんにぜひお聞きしたいことがありまして、池袋のサンシャインが建つ前にそこに何があったのか、この舞台を観る前からご存知だった方はどのくらいいらっしゃいますか?僕はあそこが始まったところから「これはとんでもないものを観ているな」という気がしはじめたんです。
ご存知ない方も多いようなので言っておきますと、あそこはA級戦犯と呼ばれる人々が処刑された巣鴨プリズンの跡地に作られたんですね。我々の世代はこれは常識だと思っていましたら、そうでもないことが非常にある種ショッキングでした。また、その後で映し出されたお墓の向こうにあるサンシャインの映像というのが、あたかも墓石のように見えてました。しかも、そこに記念碑がどうのこうのというテキストが出てきて、「そこまで言っていいのか」と思ったんですが(笑)、あの墓地はどこだったんですか? 僕がいま構想している劇映画のロケ地のひとつとしてぜひ使いたいと思うんですが(笑)。
宇賀神:まず最初に、高山さんの方から「お墓を映しながらサンシャインも見せる」という課題があったんですね。ですが僕の生活圏に池袋という都市がなくて、どちらかというと文芸座に通っていたぐらいで、サンシャインの方向にはほとんど行ったことがなかったんです。撮影助手として参加されている郷田さんという方がいて、池袋の駅に近い大学だったということで、南池袋の辺りを提案していただきました。その前に護国寺の辺りの交差点から始まって、雑司が谷、鬼子母神と、どんどん駅に近づいていったんです。そうすると池袋駅の南側に、南池袋公園というのがあるんですが、実はそこにはずいぶんお寺があるんです。あの映像よりも近い位置にお寺があったりして、こういうのはたぶん新宿とか渋谷にはないんじゃないかと思います。
藤原:実は新宿西口の高層ビル街の近くにもお寺があるんですよ。だけど別に新宿の副都心の向こうに墓地があっても別に何とも思わないんだけれども、巣鴨プリズン跡地の巨大なビルが墓地の向こうにあるというのは……あれは高山さんのアイデアだったんですか?
高山:サンシャインを使えるかなと思ってずっと考えていたんですね。でも実はあれだけじゃなくて、何十種類とサンシャインの映像を撮ってもらったんですね。高速道路とサンシャインとか。それをすべてお二人に撮ってまわってきてもらって、最終的にあれに決めたんです。
藤原:一番ベタなものを使ったわけですね。
高山:そうですね。もうこれは一番強くいくしかないなと思いました。
藤原:あともうひとつこわいのは、日本語というのは「わたし」という一人称の言葉を、ほとんど使わないですむ言葉なんですね。僕は普段から、英語・フランス語・日本語という三ヶ国語を使っているので、日本語というのは「わたし」、英語で言うと”I”という言葉をほとんど使わないなと気づくんですが、日本人が日本語だけで生活していたら、「わたし」という言葉を使わないという事実にはほとんど気がつかないと思うんです。それが、ここまで「わたしたち」という言葉を繰り返される気持ち悪さはすごいものですね。ドイツ語の戯曲を無理やり日本語に翻訳したことで、私たちが「わたしたち」という言葉をほとんど使わないということが明らかになる。私たちが「わたしたち」でいることにきわめて無自覚でいられる民族であるということが突きつけられてしまう。逆に言うと、だからこそ我々は「わたしたち」と言われることにすごく弱くて、コロッと参っちゃうんですよね。
「外国語では翻訳できない」と言われていたものを、あえて日本語でやろうという発想がすごいんだけど、それは単なる思いつきではなくて、私たちの日本語が持っているある種の危うさを突きつけられてしまった怖さがありました。
逆にこういう翻訳上演みたいなものをやると、どうしても我々日本人の受け取り方としては、その国の事情を知るために翻訳劇を観るというところがありますが、ここで突きつけられているのは実は日本人についての問題ですよね。しかもそれが、きわめてタイムリーである。「美しい日本の国」と言いながら美しい日本語も使えない総理大臣がいるこの時代に(笑)。
高山:ドイツ語で「わたしたち」というのを日本語に訳すとしたら、普通は「我々」だと思うんです。最初は文章のトーンによって、「我々」「僕ら」といった感じに言葉を分けようと思ったんですが、最終的に「わたしたち」に統一したんですね。「ドイツ人!ドイツ人!ドイツ人!」などの言葉もそのまま残しました。それによってお客さんが、「わたしたち」という言葉の怖さを自分で考えてコンタクトしてくれたりですとか、「わたしたち」という言葉と普段できないようなコミュニケーションをしやすくできるようにしました。
パフォーマーを1人にしたのもそういう理由です。「わたしたち」といっても実はその中に分裂があったりだとか、あるいはファシズムやナショナリズムを思わせるぐらいにまとまっていたりする。それを、1人の声と身体だけで表現して、あとはこういうオブジェだとか洋服だとかだけでやりたいなと思いました。
藤原:実は、僕がこれを観ていた時にふと思い出したのが北一輝なんです。知らない人も多いと思いますが、2.26事件の思想的支柱となった、いわゆる国粋主義の思想家なんですが、きわめて興味深い人物でもあります。実は北一輝の思想って、天皇がいるということ以外はほとんど共産主義なんですけれど。
この「わたしたち」の怖さ、しかも女性にしたというのが僕はおもしろかったんですが、ほとんど幽霊にしか見えないんですよね。普通、演劇というのは「生身の人間の躍動を見せる」みたいなのがあって、実は僕も基本的にはそういう演劇の方が好きなんですけれども、この舞台ではパフォーマーが幽霊のようで、しかもその声というものが、本人が喋っているときもあれば録音のような時もあって、その区別がつくのかどうなのかよくわからない。それがますます「わたしたち」という言葉の何とも不気味な空虚さ、そしてその空虚さの中に、ともすれば我々がするっとそこに吸い込まれて、その「わたしたち」であるという居心地の良さにはまってしまうということの怖さが感じられて。途中でパッと客席に光が当てられた時には、もう高山さんを殺したくなりました(笑)。一歩間違えればヒトラーの再来になれるんじゃないでしょうか、この男は(笑)。
高山:僕は演劇というと、「生き生きと躍動する身体」よりは、むしろ幽霊っぽいのが結構好きなんですよね。もう少し言うと、身体と声の間に何となく溝があって、そこが分離しているような感覚というのがすごくいいなと思います。
藤原:演劇という制度自体がきわめて虚構的な制度だから、それはそれで許されることなんだろうと思うんですけれども、そもそも演劇で「生き生きと躍動する身体を生身で体験する」というのがリアルな体験なのかというと、全然そんなことはない。実はすごく作られたイメージを見ているだけじゃないのか。特に我々のように、作られたイメージを映像というものに定着することで表現している商売だと、より観客が見ているもの、我々が観客の皆さんにご覧いただくものというものの真実がどこにあるのか、というのは堂々巡りにならざるを得ないんだけど考えざるを得ないというところがあります。
少なくとも、今日観た舞台では、幽霊であることが一番真実なんですよね。なぜなら「わたしたち」ということはある意味で単なる幻想にすぎない。もちろんその幻想はある意味で必要なものだし、幻想といってもある種現実に根ざしている部分も相当ある。実際、「わたしたち」日本人は日本語という言葉を喋り、日本という島国で共同体を作ることによって生活している。そしてその共同体がなければ私たちは生活していくことができないというのは厳然たる事実で、そういう意味で決してナショナリズムを否定するものではないけれど、ただそれが幻想であることは確かなんですよ。その幻想が今、気持ち悪く日本社会の中に増殖してしまっている不気味さというのがあります。単に日本というナショナリズムの幻想だけではなく、家族という幻想もものすごく広がってきてしまっている。その裏にあるのが、家族が崩壊しているだとか、日本という民族の中心であるはずの日本語という言語がきわめて危機的であるとかいうことです。何しろ「美しい国日本」と言っている総理大臣が、所信表明であそこまでカタカナを使って、あげくにナショナル・アイデンティティと言うべきところを、カントリー・アイデンティティというわけのわからない造語まで使ってしまったという(笑)。
実はそういう時代の危機感を皆が感じているからこそ、「わたしたち日本人」という言葉は使っていないにせよ、それをすごく押しつけられている気持ち悪さというのを、無意識に皆さんも感じてしまっているんじゃないかなと思います。しかし一方で、それが欲しいという無意識もあると思うんですよ。その無意識を、こうして見事に舞台として見せられてしまうと、正直言いましてきわめて不愉快ですね。いや、いい意味でですよ(笑)。途中で本当に逃げ出そうかと思った時が何度もありました(笑)。
林:そう言っていただけると非常に嬉しいですね。演劇というのは、劇場という閉ざされた空間で、これから皆さんが見るものは作り物ですよという前提のものに行われるわけですよね。でも藤原さんがこうやって、そういうものを見ている中で、劇場の外のことをたくさん考えてくれて、いまの日本や社会のことについてすごく考えていただけたというのは、やはり作品のそこここに、「生き生きとした役者の身体」だとか、そういうものではない生の現実というものが出てくるからでもありますよね。アジアからの留学生だとか、池袋のインタビューだとか。あの池袋のインタビューというのも、このお二人をはじめとした映像・音響スタッフがサンシャイン周辺でいろんな人に声をかけて集めてもらったものなんですが、サンシャインの脇がいまは公園になっていて、処刑台跡地が石碑になっています。そういうところでスケボーしてたり自転車乗って遊んでいる人たちや、いろんな若い人たちにインタビューしていて、どういう感じだったのかということを三行さんからお話してもらえますか。

(C)松嶋浩平
三行:これまでの舞台で、実際に今回のようなインタビュー映像を使うこともあれば、インタビュー的なことを舞台に挟んでいくということもあったんですね。いろんな形でそういった外部性というものを使っていて、その外部性のようなものが、映像を使うもっともな理由だと思っています。『Re:Re:Re:place 〜隅田川と古隅田川の行方(不明)〜』という舞台をやった時も、同じような形でインタビュー映像を使いましたが、今回インタビューを進めていく中で、僕自身がある変化を生じたことがありまして、それが建国記念日の日だったんです。
サンシャインのすぐ脇に、東池袋公園という元処刑台だったところがありまして、そこに石碑が建っているんです。それまでそこには誰も寄りついていなかったんですけれど、その日だけはそこに手を合わせたり拝んでいったりする人が結構いて、僕はそれを見た時に、民族だとかを超えた、人間の太古からある営みみたいなものを見た気がしました。消えていく、無くなっていくものを記憶するために石に刻むということですね。
僕はそのインタビューをしている時に、まだ観たこともない映画が気になっていたんです。ミシェル・クレフィという監督の「石の賛美歌」という映画なんですが、テレビでミシェル・クレフィが「石というのは現実であり、インティファーダである」というようなことを言ってたんです。僕はその時それがよくわからなかったんですが、その光景を見たときに「あ、なるほど」とわかったんです。消えていく、無くなっていくものを、現実に残していくためのものとして石がある。
藤原:「石の賛美歌」はパレスチナの映画で、第一次インティファーダが始まって2、3年後に作られたものですよね。
ちなみに私はその映画を観ているんですが、日本だと山形国際ドキュメンタリー映画際で91年に上映されています。そして補足すると、パレスチナ人にとっては、石というのは奪われた大地そのものになってしまうんです。これはこの芝居のテーマとすごく関わってくる話なんですが、日本人は幸いにして、めったに国土を奪われたことがないのでそういうことを考えないのですけど、象徴的な意味での「大地」という言葉がある一方で、そこで何十年何百年、先祖代々生活してきた土地という意味がある。その二重性というのが、一歩転ぶと大変に怖いことになってしまうという、今のパレスチナもちょっとそうした状況を感じます。
三行:だからお墓とサンシャインの映像というのは直接的ですけれども、やっぱりこうやらなきゃいけないと思いました。インタビューということで言えば、普通こういうのはインタビューする側が聞きたいことを聞くはずのものなんですが、僕にとってそれが自分が聞きたいことなのかというと、そうでもなかったんです。でもやっぱり聞いていくとおもしろかったですね。
宇賀神:最初は、僕らの世代というか、若い人たちは巣鴨プリズンのことはほとんど知らないんじゃないかと思ったんです。そうしたら、実はそうでもない。それは僕にしてみると結構驚きでしたね。明らかに地元の人は知っているというのがありますね。
そしてその公園でインタビューをしていたりしたんですが、実はその石碑を避けるように撮影していたりしたんです。
藤原:そうですね。そこがまたいいなと僕は思いました。
宇賀神:そこは何度も議論したんですけれども、あんまり直接的すぎるのもどうかなと考えたんです。
藤原:そこが表現というもの難しさで、あまり直接的なものを入れてしまうと、説明だけで終わっちゃうんですよ。だけどそれだったら舞台とか映画という形でやる必要はなくて、テレビのニュースでやればいいんですよね。
宇賀神:サンシャインビルの入り口の、隅っこの方に石碑があるんですね。表に「永久平和のために」と書かれてあって、裏面を見ると「軍事裁判によってA級戦犯の刑が執行された」という文字が書いてあるんです。それを読んだ時には、大げさかもしれないですが僕もちょっと歴史を背負ってしまったような、「えらいものに会っちゃったな」という感じがしましたね。もしサンシャインに行かれる方がいらっしゃったら、ちょっと覗いてみていただきたいなと思います。
藤原:考えてみたら「A級戦犯が靖国でどうこうした」という時、「A級戦犯」という言葉は知っていてもそれが何なのかということがほとんど知られていないんじゃないかと思います。日本人の歴史の受け取り方というのは考えてみたらものすごく不気味で、「A級戦犯が靖国でどうこう」というニュースは流れていますが、じゃあA級戦犯が何なのかということをちゃんと認識したうえで報道しているかどうかも怪しい。そういう風にすごく曖昧だからこそ、「わたしたち」と平然と言えるんだろうなと思います。そういう意味で、この文章は本当にいやらしい文章だと思うんですが(笑)、そもそも何でこれをやりたいと思ったんですか?
高山:『雲。家。』というこの戯曲を素晴らしいかたちで演出した演出家がいまして、彼が「これは日本語では絶対不可能だ」と言ったんですね。それで「そうかな?」と思ったんです。
藤原:彼らはたぶん、我々が同盟国だったことを忘れているんですよ(笑)。
高山:でもさっきの話に戻ると、僕は右か左かという区別でいえば、たぶん左寄りの人間だと思うんですよ。それで巣鴨プリズンを調べていくと、あそこはA級だけじゃなくて、B級、C級戦犯と呼ばれる人たちも処刑されているんですね。僕はそっちの方も問題だと思っていて、裁判の仕方にしろ、どういう人が選ばれて処刑されたかというと、ほとんどくじ引きみたいなものなんですね。そこを、彼らは戦犯だから別にいいんだと言って、私たちの外部に切り離していいかというと、なかなかそれは難しいぞというのは、今回本当に考えさせられました。しばらくは態度保留という形でいくしかないなと思っています。
藤原:僕自身は、基本的に自分は極左だと思っているんですけれども、一時期靖国神社にしょっちゅう通っていたんですよ。実は特攻隊の生き残りを取材するという企画がありまして、いま宙吊りになってしまっているんですが、そもそも天皇制のことをやろうと思って皇居に取材に行った時、たまたま皇居の喫煙所で会ったおじいさんが特攻隊の生き残りだったんです。月に一度、特攻隊の生き残りの人たちが集まる会というのがありまして、それは世田谷区の世田谷観音というお寺なんですが、そこに特攻観音というものがあるんです。毎月18日に縁日があるんですが、そこで特攻隊の生き残りだとか遺族だとかが集まるから、来てごらんなさいよなんて言われて、のこのこ行ってみたんです。そうしたらおもしろいから、しょっちゅう行っていたんですね。僕は軍国主義はとんでもないと思っている人間だから、ある意味で居心地が悪いんですね。でもその人たち自身はすごく真面目でいい人たちなんですよ。じゃあその時代の日本人が全員狂ってしまっていたのかというと、そんな単純な話ではない。
僕が最初に会ったおじいさんは、「天皇のために死ねって言われたんですよね」と聞いたら「そんなことは後から格好つけて言っただけで、なんとなくその場の雰囲気で行くことになってしまっただけだ」なんて言うんですね。
後でその方に詳しく聞くと、当時17歳くらいで、ある日司令官に会いに行くと「お前を特攻隊に選んだ」と言われた。その方は司令官と同郷だったらしいんですね。「悪いけどちょっとお前やってくれや」と言われて、「世話になってるからしょうがないか」と思って受け取っちゃった。
学徒動員で特攻隊になって生き残った人たちの会話も聞いたんですけれど、「日本もこんなとんでもない戦争のやり方をやるからには、これはもう絶対負けるに違いない。でも負けるんだったら、日本人がいかに気が狂っていて危ない民族であるかということをアメリカに見せつけなければ、負けた時にお袋や妹が何をされるかわからないから、講和条約を少しでも良くするために、この際俺たちは死のう」ということだったらしいんですね。狂ってはいるんですけれど、筋は通っている。
だから決して「神国日本」とか言っていたわけではないという、その妙な乖離や、靖国神社ということも含めて、最近考えざるを得ないのは、その時代についてものすごく健忘症になっているということです。なぜああいうことが起こったのかということを、軍国主義のせいであると言ってしまうことのやばさを感じます。それは実はわたしたちの問題であるのに、それを「軍国主義」でごまかして、日の丸君が代の問題だけにしてしまうということはすごく不健全なことで、その不健全さを改めて突きつけられたような気がするんです。
日の丸君が代というのも、あんなものは幽霊なんですね。A級戦犯だけが悪いわけではないというのは当時の人たちは皆気づいていたし、A級戦犯自身の人たちも、この際誰かが処刑されなきゃしょうがないから俺たちは人身御供になるんだと、特に東条英機はそう考えていたふしが相当にあるんですね。もちろん彼の責任は相当大きいんですが、あの人は無能なお役人であったということが最大の罪であって、別に彼が戦争をやると言ったわけではない。実はすごく集団的な責任であることが、それを誰かに押しつけることによってごまかされている。それを日本人は「軍国主義」ということで自分たちを許してしまったし、日中国交正常化の時も、要するに軍国主義が悪かったので日本人は悪くないという屁理屈を周恩来先生がひねり出してくれたから、日中国交正常化したわけですよね。それで総理大臣が靖国へ行ってA級戦犯に拝んだから「それはいくらなんでも約束が違うだろう」と怒っているだけなんです。しかしそのことすら忘れている私たち日本人というのがいて、だけど「美しい国日本」とか、そういう空虚な、実体験ではない言葉だけはものすごく氾濫してしまっている怖さをすごく感じます。
それが戦後60年で変わるかもしれないと僕は思っていたんですね。僕がその特攻隊のおじいさんと付き合っていたのは戦後60年の時だったんですが、その時に、これまで語らなかった人たちが出てきたんです。それで特攻隊の企画をフジテレビのプロデューサーのところに持ち込んだら恐ろしいことが起こったんです。会いに行く日に福知山線の脱線事故が起こって、一週間後にやっと面会に行ったんですね。それで、特攻隊のひとつの大きなテーマになるのが、生き残ってしまったということとどう向き合うのかということだと言ったんです。そしたら、深夜放送を見ている若者にはそんな難しいことはわかりませんよと言われてしまったんです。生き残った者の罪悪感なんて、現代の若者にはわからないし通じるわけがない、と言ったその三日後から、福知山線の事故で生き残った人たちが「生き残って申し訳ない」ということをテレビで言い始めたんです。あれは気持ち悪かったですよね。というのは、特攻隊の生き残りにしてもホロコーストの生き残りにしても、大体2、30年かかってからようやく言い出すんですよ。それが、そういう言葉が直後に出てくるということが、そのことを演じなければいけないと思われているいうことですよね。
先程「躍動する身体」ということを言いましたが、演劇において実は「躍動する身体」というイメージを受け取っているだけじゃないかという気がします。すべてが表層的な言葉に集約するイメージだけで消費されていく時代になってしまっているような感じがして、僕はそれがすごく怖いんです。しかしそういう傾向に反対する映画を作ると、映画祭とかではそれなりに評価していただけるんですが、配給会社が全くつかなくて「君の映画は商売にならない」なんて言われてしまうんですが(笑)。だから僕は、高山さんがこれを幽霊の話にしたのが賢いと思うんです。まさに一見我々がリアルだと思っていることが幽霊だと思ってしまっている。
林:思わぬ方向におもしろく話が進んできたと思うんですが、この舞台ではとりわけあからさまに政治的な問題のみを扱っているわけではないですよね。もちろん、合間合間にサンシャインや留学生の映像が入ってきているんですが、80分間政治的な問題を全面に扱っているわけではないと思うんです。そういったことについて、高山さんにお話していただきたいと思います。演劇をやるうえで、そうした社会的な問題をどう扱うのか、どこまで扱わないのか、お話ししていただけますか。
高山:さっきのお墓の話でもあったんですけれど、政治的な問題を扱うか扱わないかというところであまり線を引きたくないというのがあるんです。ドイツでは特に、政治的な問題を扱っていたら○(まる)、扱っていなかったら×(バツ)みたいなところがあるんですね。
藤原:しかも、その扱い方がある種規則みたいになっているところがありますよね。
高山:そうですね。何だかアリバイ作りみたいな気がして、そういうのはよくないなと思います。さっきのお墓とサンシャインと映像ですが、「これいいな」「これ使えるな」という基準というのは、フレームも含めた強度なんですね。
藤原:あれは言われてみないとわからないけれど、見た瞬間に、ほとんど笑えますよね(笑)。
高山:そのぐらいの感覚がないと、本当に説明だけで終わってしまうんです。政治的な説明だけで終わるんだったら、本を書いたり政治運動した方がいいんですよ。そういう問題を扱う扱わないとは別に、またもし扱ったとしても、それを演劇でしか体験できないような強度というかおもしろさで見せたいと思います。
藤原:今は特に政治的言語と呼ばれるものが、ものすごく上っ面なんですよね。だから政治を語ること自体、我々がどう生きるかとかどう生活するかということと直結しているはずなのに、すごく上っ面な言葉になってしまっているし、言葉自体がすごく力を失っているということを、最近僕はつくづくと感じています。
僕は映画監督なので、言葉よりも映像というところはあるんですが、映画にだって音がありますからね。その時に本当に心に響く言葉、上っ面ではない言葉をどう取り戻すのかというのはすごく重要な問題だと思うんです。特に日本語という言葉は、我々は誰も気がついていないんですが、すごく人工的な言葉ですよね。その人工的な言葉を、しかも翻訳したものとして舞台でやるというのはどういう意識からだったんでしょうか。翻訳をされた林さんは結構苦労したんじゃないかと思うんですが。
林:苦労しましたね。「翻訳不可能性」とか、格好いい言葉をパンフレットに書いてあったりするんですけれど、翻訳というのは基本的には不可能なわけですよね。「わたしたち」という言葉は英語だったら「we」ですが、「わたしたち」という言葉と「we」という言葉は、見た目の感じも違うし、音の長さも違うし、意味だけだったらイコールになるのかもしれないけれど、本当は絶対にイコールじゃないんですね。だから基本的に翻訳というのは不可能なんです。「we」という言葉を「わたしたち」とした時に、「we」は一音節なんだけど「わたしたち」という言葉は五音節あって、非常にまだるっこしくなる。ドイツ語でいえば「wir」なんですが、これがたとえば、もしドイツ語で「wir, wir, wir」という言葉があるとすると、日本語だと「わたしたち、わたしたち、わたしたち」になる。そうするとまだるっこしさが倍加されるわけですね。
エルフリーデ・イェリネクというのは、演劇学とかドイツ文学だけじゃなくて、ウィーン市立音楽院でオルガンと作曲を修めた音楽家でもあるんですね。そして彼女の文体というのは、その政治的な内容や凝った技法というもの以上に、そういった感覚的なところが素晴らしいんです。なのでドイツ語を意味の上でわかりやすい日本語にするのではなく、多少日本語が変形しようが奇形になろうがかまわないで、むしろ日本語がドイツ語に出向くような翻訳をした時に、もしかしたら日本語でしかできない言葉の可能性があるんじゃないかと思ったんです。つまり翻訳が不可能であるが故に、翻訳の可能性というのがあるんじゃないかということです。だからそれを体感していただけたというのはすごく嬉しいですね。
藤原:体感しすぎて気分が悪くなってしまいましたね(笑)。
高山:(床に広がっている書を指して)この文字も、これがドイツ語から翻訳されてここにあるという感じになっていて、たとえばこれをドイツ語に翻訳できるかというと、絶対できないと思うんです。こういう字体とか書体とか濃淡というものを舞台に反映したいなと思って、これをお願いしました。
林:今回のアフタートークでは質疑応答の時間というのは設けておりません。今回は毎公演後、裏のロビーにビールやワインを用意しておりまして、私たちPort Bのメンバーも藤原さんも当分残っていますので、ご感想やご質問を聞かせていただける方は、是非そちらでゆっくりとお話していっていただきたいと思います。とりあえずトークの方はこれで終わりとさせていただきます。どうもありがとうございました。