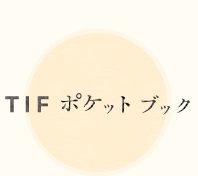3月4日(日) ポスト・パフォーマンス・トーク
トーク出演者
高山明(Port B)
林立騎(Port B)
佐伯隆幸(学習院大学/演劇批評・フランス文学)
藤井慎太郎(早稲田大学/フランス語圏舞台芸術・表象文化論)
林:本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。これからポスト・パフォーマンス・トークを始めさせていただきます。今回テキストの翻訳とドラマトゥルクを務めさせていただきました林と申します。
まず本日のゲストをご紹介させていただきたいと思います。こちらが藤井慎太郎先生です。藤井先生は早稲田大学の助教授でいらっしゃいまして、フランス語圏の現代舞台芸術と、文化政策や芸術政策ということに関心を持たれて、多数の論文を発表なさっています。また、舞台上演のために多数のフランス語戯曲を翻訳なさっていらっしゃいます。そしてその奥が、佐伯隆幸先生です。佐伯先生は学習院大学教授でいらっしゃいまして、現代演劇に関する多数の著書を刊行なさってます。それから、ベルナール=マリ・コルテスの戯曲の翻訳も出版なさっています。そして一番奥が、Port B構成・演出の高山さんです。
高山:今日はどうもありがとうございました。今日は実は楽日であまり時間がないので、こちらで20分くらいポストトークをやった後、後ろのロビーにビールやワインを用意してありますので、そこで続きをやりたいと思います。
早速トークを始めさせていただきたいと思いますが、まずは今回の舞台を観た率直な感想を聞かせていただけますか。
佐伯:私はとてもおもしろかったです。以前に「舞台芸術」でも書きましたが、私は日本の芝居は「演ずる演劇」で駄目になっているから、「読む演劇」というのをやった方がいいと思っているんです。
今日の芝居は読む演劇でしたが、つまり読む演劇がどうしていいのかというと、どこを読んでもいいわけですよね。頭から最後まで読む必要はなくて、途中開いたところから読んでもいい。そんな風に舞台を拵えたほうがいいと私はこの頃思っています。
基本的にはリーディングでいいし、下手な俳優が舞台でかさばるなと私なんかは思います。私の昔の友人である津野海太郎が「芝居は品である」と言ったんですけれども、今の芝居は品がない。つまり肉体が無意味にかさばっているんです。ここで怒り出すときりがないので、藤井さんにお願いしたいと思います。
藤井:初日も拝見したんですが、初日は腑に落ちる部分と腑に落ちない部分がはっきりしなかったんですね。ただ、今日もう一度拝見して、それから先程の佐伯先生のお話を伺って、だいぶはっきりしてきました。先程、佐伯先生が「読む演劇」ということを仰いましたけれども、読むだけじゃなくて「聞く演劇」という部分で、非常に深く感じる部分がありました。フランス語で「ささやく」というのをスフレモという言い方をするんですが、言葉を息にのせてそっと吐き出すという意味なんです。言葉を息にのせて吐き出しながら、それが暁子猫さんの息遣いを聞くようなそういう瞬間でもあるというのを感じました。言葉というのは、書かれた文字はなくならないわけですが、聞く言葉は聞く瞬間に消えていってしまう。消滅する部分、消えてなくなる部分、空虚に還元されていく部分というのが、今日は非常によく聞き取れました。
先程の佐伯先生のお話に引きつけると、日本の現代演劇全体の身体というのは、無理に身体をいっぱいにしようとして失敗している部分があると思うんです。しかしからだというのは「から(空)」なわけですから、その空の器として存在している部分が非常によく見えてきた。このテキストで繰り返されている「わたしたち」という言葉を空なものとして、うつろなものとして読んだときに、「わたしたち」というのがそれほど強固なものなのか、家というのがそれほど強固なものなのか。高山さんの演出だと、家というのが非常に隙間だらけの、家というよりも空っぽの空間に近づいていくような感じがあります。それが巣鴨プリズンであったりとか、消えてなくなるものと重ね合わされたときに、初日には引けなかった一本線が引けたような気がして、非常におもしろかったです。

(C)松嶋浩平
佐伯:家というのは、第一世界の典型であるドイツということじゃないんでしょうか。家はつまり世界史の中の文明だと思うんです。ぼろぼろになっているけれど、原理としては依然として残っている。私たちのいる世界というのが、映像に出てきた若い子たちも含めて強固に文明というのは存在している。しかし「ここにいる」と繰り返しているところを見ると、どうやら「ここ」ではない、文明から遠い世界も存在している。それはドイツの中のトルコ人かもしれないし、フランスの中のマグレブかもしれない。だから高山さんの舞台を政治的に読むことは可能ですが、私はそうは読まなくて、記憶というものをめぐるヘルダーリン的な芝居だと思いました。藤井さんの話で言えば、音声ですね。「読む演劇」というのを提唱したときに私が考えたのは、言葉に回帰するということではないんです。
数日前にチェーホフの『プラトーノフ』を観たんですが、私はあの作品が他に比べると好きなんですが、結局「私は誰なのか」ということばかり話しているわけです。時間つぶしの演劇だと思うんですが、チェーホフというのは「私は誰なのか」ということに初めてつまずいた時代なんですね。そして最後の時代だと思うんです。「私は誰なのか」というのは今だったら出来ないと思うんです。私はいまここにいて喋っているわけですが、喋っている音声があるのであって、私が思考していることが喋られているわけではないと思うんです。佐伯隆幸という人が喋っているわけですが、純粋な音声だけである。ささやき、つまり息にのっている音声というものがどう音楽的に聞こえてくるかというものの中に記憶が入ってくるのであれば、言うことはないと思うんです。記憶と世界史というものが両方あるとして、世界史というのは私たちが学校で教えてきた、私たちを縛っているものですよね。私たちは世界史の中で決して自由ではない。記憶というのは私たちの身体がおそらく持っているものだと思います。
「読む演劇」「聞く演劇」というのは、コルテスでもあるしクローデルでもあるし、アルトーでもある。アルトーとクローデルは両極ですが、実は問題は「息」なんです。音声をやれない人間が俳優をやってもしょうがないと私は思うんですが、そういう意味ではトークやシンポジウムというのも演劇的だと思うんです。ついでに言えば舞台よりも何よりも、表方が一番演劇的でなくてはいけないと思います。
高山:佐伯さんが仰ってくれたことはすごく大事な問題で、僕が声ということを考え始めたのは佐伯さんの本がきっかけなんですね。15年くらい前になりますけれども、佐伯さんがパリで観た芝居について書かれていて、最後のシーンで舞台にラジカセがおいてあって、ヴェルディが流れていて感動したということが書いてあったんです。それがすごくいいなと感じたんですね。その後にグリューバーの稽古を見る機会があったんですが、彼は人物と人物が話しているように見えるとすごく怒るんですね。違う、声と声が話しているようにやるんだ、と言って、そういうのをやりたいなと思ったんです。そこから少しずつ、人物とか身体というよりは、藤井さんが仰ったような声と人物が分離しているようなものを探求しはじめたんですね。
佐伯:新国立劇場の研修で喋ったことを一言だけ言わせていただきたいんですが、男と女がたとえば抱き合ったときに、これを男と女の関係だと思うのは間違いなんです。これはただ皮膚と皮膚が触れ合っているに過ぎないというのを、表現としてどう取り戻すかというのは、実はすごく難題なんです。男と女がこうやったら、男と女の関係があると自明に思う、私はそれは違うと思うんです。肌と肌が触れ合ったにすぎないという質感をどう出すか。これは言語でも同じだと思うんです。言語が自明に背負わされている質感、近代的な約束の中での意味というのを、どうやって外した質感をもてるかというのが、僕は言語に限らず表現にとっては一番大事なんじゃないかと思います。
高山:まったくその通りで、僕もそこに賭けたいなと思っています。藤井さんのお話ですごくおもしろいのが、最初に天文学をやられていたんですよね。それが、どうも自分は文系の方がいいと思われて、フォーサイスの舞台を観てそちらに転向された。フォーサイスの舞台も、そういった質感というのを僕はすごく感じるんですが、そこを絡めて最後をまとめていただけますか。
藤井:やはり、観てておもしろい舞台というのは、そこに見えないものを感じさせる舞台であったりとか、見えないものを見ようとする、不可能なものへと導かれていくようなものだと思います。だから高山さんの仕事を拝見して、おもしろいと思うし、応援したいと思うんですね。これは観客に受けないかもしれない、それに理解されないかもしれないという題材をいつも持ってきていて、だから完全に「わかった」とは言いきれない舞台が多いのだけども、それでも何とかしてそのぎりぎりのところで観客とコミュニケーションをとろうとする、その姿勢が日本の演劇界に決定的に欠けている部分のような気がするんですね。
常々僕が思うのは、演劇などの舞台芸術というのは、フランス語でスペクタクルヴィヴォンと言って、ヴィヴォン、つまり「生きている」という言葉を使いますが、実はそれは違うと思います。むしろ生きているそばから死んでいく、死に支えられている芸術だと思うんです。そういう消えていくもの、その場に永続しないものというのを感じさせてくれる舞台芸術というのが少ないと常々思っていますが、今日の舞台は映像を見ても、確固たるものというよりはうつろなもの、移り変わっていくもの、空虚なものを孕んでいますね。ドイツのものを扱いながら、日本的な原点にも立ち返っているような。主人がいなくなった衣服があったりだとか、誰が書いたかわからないけれど痕跡として残っている書があったりだとか、俳優の身体でさえも、この紗幕に遮られて、映像として映っているのか本物なのかわからない、うつろなものとして出てきた。現代芸術の中で、僕が一番おもしろいと思っているものに通じる部分が出てきたと思います。
佐伯:うつろな一瞬を徹底すれば永遠なんですよね。同時代の特定のショットを捉えれば、それは永遠のものになりますよね。演劇が抱えている不純さと強さと弱点がそこにあるんだと僕は思います。文字は残るけれど演劇は残らない。だけど残らないが故に永遠を照らすんだと私は思いますし、そういう場所から自分や他の人の仕事を見たいと思います。
高山:ありがとうございました。先程佐伯さんが、表方が重要と仰ってましたが、公演やトークが終わってから展開していくものもすごく重要なことだと思うんですね。そういうことを、ドラマトゥルクの林がかなり考えてやってくれていて、もちろん他の方の協力も得ながらですが、これからもこういう形で展開していきたいなと思います。それでは、これから場所を移動する形でロビーで続きをやりましょうか。今日は本当にありがとうございました。