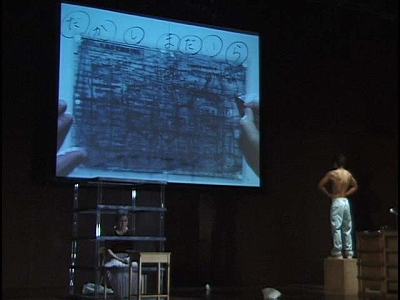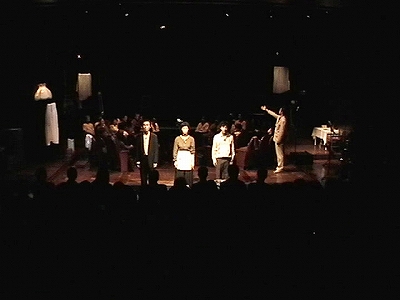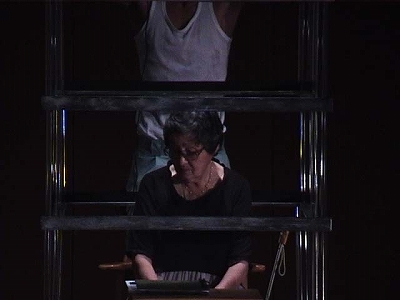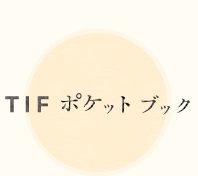Port B ���R�������O�C���^�r���[
�����ȊO�̊����Ɍg���A�[�e�B�X�g�E�E�l�E��]�Ƃ�𒆐S�ɉ����I�������J��Ԃ��A�u�����Ƃ͉����v��₢�Â��Ă���Port B�B����̓������ی|�p�Ղł́A�u�O���ł̏㉉�͕s�\�v�Ƃ�����G���t���[�f�E�C�F���l�N�̋Y�Ȃ���{���㉉����B
Port B�̉��o�ƁE���R���͉��҂Ȃ̂��H�@Port B�͉������ł���̂��H
Port B�o���҂̋Ŏq�L�A�h���}�g�D���N�̗ї��R�ƂƂ��ɘb���f�����B
�i������FTIF�X�^�b�t�{��E���c�j

���[���b�p�ł̕��Q����
�����������f�ނɂ����܂킵�Ă��炤
�l�ɔC����������ɂ������̂��ł���
�����ł������Ȃ���������肽��
�l���W�܂��Ƃ��ĉ������@�\��������
���q����ɍ���Ă����Ă��炢����
���[���b�p�ł̕��Q����
�{��F���R����̃v���t�B�[����q������ƁA20��̂Ƃ��ɓn������ĕ��Q����������Ă����Ə�����Ă���܂��B�ǂ������������Ń��[���b�p�ɓn�낤�Ƃ��ꂽ�̂��A�܂������łǂ̂悤�Ȍo�������ꂽ�̂������b���������Ȃ��ł��傤���B
���R�F�ŏ��ɓn���������������Ƃ����̂́A���̓h�C�c��Ȃ�ł���B�h�C�c�������Ă��āA�l���K���Ă����搶�̏Љ�ŁA�t���C�u���N�Ƃ����A�X�C�X�ƃt�����X�̍������炢�ɂ��鏬���Ȋw���̊X�ɍs���܂����B�����ɍs���āA�h�C�c�������邽�߂ɂƂ肠������w�w�Z�ɓ�������ł��B�t���C�u���N��w�Ƃ������\�D�G�ȑ�w������������A���̂܂ܑ�w�ɐi��ŁA�h�C�c�̓N�w������悤���ȂƎv���Ă܂����B���ꂪ��w�w�Z�ɓ�����3�����キ�炢�ɁA���܂��܊X������Ă�����A�s�[�^�[�E�u���b�N�́w�Ȃ�X�q�ƊԈႦ���j�x�̃|�X�^�[�������Ăł��ˁB�������낻�����Ȃ��Ǝv���āA�V���g�D�b�g�K���g�ɍs���Ă��̕�����ς���ł��B
�������������Ȃ�đ債�ĊS���Ȃ�������ł��B�����ǁA�������Ƃ��������D���ŁA�Y�Ȃ������Ă���ł��ˁB�Y�Ȃ̌`���݂����Ȃ��̂��������D���������̂ŁA�������Ăǂ��������̂Ȃ낤�ȂƂ͎v���Ă܂����B���ƁA���{�ɂ����Ƃ��A�s�[�^�[�E�u���b�N�́u�����Ȃ���ԁv�Ƃ����{���������������납�������Ă����̂ƁA��w�̎��ƂŌ����Ă�����Ă����A�^�f�E�V���E�J���g�[���́w���̋����x�A���ꂪ�l�ɂƂ��Ắu�����v�ŁA���Ƃ͂���܂苻���Ȃ�������ł��B
�����ǁA���̃s�[�^�[�E�u���b�N�̎ŋ������������ǂ�������ł��B�{���ɏՌ��I�ł����B�ŁA���܂��܂��̔ӂɁA���傤�ǃp���ɍs���\��𗧂ĂĂ��āA��s��Ԃɏ���ăp���ɍs������ł��B�p���ɒ����ĉw�łӂ�ӂ炵�Ă���A�����d�Ԃɏ���ăV���g�D�b�g�K���g����p���܂ŋA���Ă��Ă��l�����܂��āA���ꂪ�u���b�N�̂Ƃ���Ŗ��҂���Ă郈�V���c��������ł��B�u����A���̐l�������ɂ����ȁv�Ǝv���Ęb����������ł��B�u�������������납�����v�Ƃ��B����Ńz�e���܂ňꏏ�Ƀ^�N�V�[�ɏ���āA�����̘b�����܂����B��������Ă�̂��ƕ�����āA����ĂȂ����NjY�Ȃ͏����Ă�A�����@����猩�Ă��������݂����Ȃ��Ƃ�}�X���������āA���Ƃ���Y�Ȃ𑗂�����ł��ˁB��������莆��������āA���܂��傤�ǃx�������̃V���E�r���[�l����Ōm�Â��Ă邩��A�����������������猩�ɗ��Ȃ����݂����Ȃ��Ƃ������Ă����āA�܂�������Ɣ`���Ă݂邩�ȁA�݂����Ȋ����Ńx�������ɍs���āA�������瑫�݊O�����Ƃ���������B
���̌�͂����A��w�w�Z����w����؍s���Ȃ��ʼn����̐��E�ɓ������������ł��ˁB���c������Ă炵���V���E�r���[�l�ł́A��{���������Ƃ����Ȑl���W�܂�̂ŁA���������l�����Ƃ��܂蓖���ł��Ȃ������h�C�c��Řb�����肵�āA�u����������悪������ǁA�`���Ă݂Ȃ����v�ƌ����čs������B
���v���ƁA�h�C�c�ꂪ���܂�ɂ��ł��Ȃ���������A�����ꂪ�~���������̂��ȂƂ����C�������ł����ǂˁB�h�C�c�̐V����ǂނƁA������]�╶�����̈�ԃg�b�v�ɉ����������ł���B������u�����Ō��ʂ��c����A�h�C�c�������ȁv�݂����Ȋ����Łc�B
�ꓯ�F�i�j

���R�F�����A���܂�ɂ������̂��Ƃ�m��Ȃ���������A���ꂩ��3���������炢�A���[���b�p���̉��������ĉ������ł��B�x�������e�s�s�A�h�C�c�A�t�����X�A�X�C�X�A�C�^���A�A�C�M���X�ɍs���āA�t���C�u���N�̃A�p�[�g�ɂ��قƂ�NjA�炸�ɔN��400�{���炢�ς܂����ˁB�����Ղɍs���A���3�{�A4�{�ς�邩��A���������̂��ςāA�Ɩ��≹���̎d�g�݂Ȃǂ��m�[�g���Ƃ��ĕ����܂����B���̂����ɁA�u����͌��\�ȒP�ɍ�ꂻ�����ȁv�Ǝv������ł��ˁB
����ŁA�F�Ɂu�����͉��o�ƂȂ��ǁA���o�����Ă��炦�Ȃ����v�ƉR�������Ă܂������ł����ǁA�Ȃ��Ȃ���点�Ă��炦�Ȃ��B���傤���Ȃ�����A���܂��܊w�����c�ʼn��o�Ƃ����N�����Ď��߂�������Ƃ����Ƃ��낪�����āA�����Ń}�b�N�X�E�t���b�V���́w�h���E�t�@�����邢�͊w�̈��x�����o���邱�ƂɂȂ�����ł��B���ꂪ�o��l����15�l���炢�����ςȌ��ŁA���̂�������������ł��ˁB���ꂪ���܂������Ă���܂��ʂ̓W�J���������̂�������Ȃ���ł����ǁA���܂������Ȃ�������ł���ˁB�ȒP�ɂł���Ǝv���Ă��̂��A���͓���āA���肷��ƕ��䂪�߂��Ⴍ����ɂȂ�A�Ƃ����̂Ŋ����܂����B�{���ɒp���������āA��������������肽���Ƃ����̂͂����������Ƃ��Ǝv���܂����ˁB�ł����q����̒��ŁA�����I�ɖʔ����Ǝv���Ă��ꂽ�l�����āA���̎d���������Ă�����ł��B�u���͂��܂��������낤�v�Ǝv���Ă��B������Ƃ܂��ɂȂ����B��������ĉ��ƂȂ��q�����Ă�������ł��ˁB�l���ǂ������̂��A�t���C�u���O�Ƃ��������Ȋw��������̊X�ɂ������Ƃł��ˁB���������ʼn��Ƃ��Ȃ����Ⴄ�Ƃ�������邵�A�X�̉����l�Ƃ��A���Ƃ݂�Ȓm�荇���ɂȂ����Ⴄ�B�����ꏊ�ł�点�Ă�����Ă������Ƃ������āA���\���q����͖����ł����B���ꂪ�x�������������炽�Ԃ�_���������Ǝv���܂��ˁB
�����1�N�����炢�������ł����ǁA�������Ɍ��E����������ł��ˁB����͐^�ʖڂɕ����Ȃ��ƃ_�����ȂƎv���܂����B�����Ă��Ȃ��ƁA�������Ƃ��J��Ԃ������o���Ȃ��Ȃ����Ⴄ��ł��ˁB�V�������Ƃ��Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��B���s�������Ȃ��Ƃ����ςȍ��������āA�����悤�ȕ������Ă�����ł��ˁB
���̍��ɑ傫�ȏo��������āA����������A�n���u���N�̃h�L�������^���[�̉f��ē���{�������Ă�����ł��B���̖{�����傤�NJJ���邩�J���Ȃ����̎��ɁA�܂��X�ւ�������ł��ˁB��������2�̗X�֕�����������ł��B�f��ē��瑗���Ă����̂��A�x�����~���́u�x�������̗c�N����v�B����1�́A���s�ɂ���l�̗F�l���瑗���Ă����u�w�x�������̗c�N����x��ǂށv�Ƃ����C�m�_����������ł��B���ꂪ�������ɗ�����ł��B���݂��S���m��Ȃ��l����B����Łu����͂��Ԃ�ǂ܂Ȃ����Ⴂ���Ȃ���Ȃ����낤���v�Ǝv���ēǂ�A���ꂪ�l�ɂƂ��Ă��������������납�����B
�N��400�{�Ƃ��ŋ����ςĂ��A�������{���ɂ������낢�Ǝv������̂��Ă���ȂɂȂ���ł��ˁB����͖l�̌�w�͂Ƃ��A�������ς�͂̂Ȃ��ɊW���Ă���̂�������Ȃ����ǁA�����̐����Ȋ��o�͂Ȃ��Ȃ����܂����Ȃ��B�u����܂肨�����낭�Ȃ��Ȃ��v�Ƃ��v���Ȃ���ςĂ����A�����������̂��������낭�Ȃ��B
�����ǁA���̖{��ǂ�ł�����A�����������������������Ă������ȂƎv������ł��B�u�x�������̗c�N����v�Ƃ����̂́A�x�����~�����c������ɂ��������x�������̂��Ƃ��l�I�Ȃ��̂Ƃ��ď����Ă�����ǁA���̌l�I�Ȃ��̂��Љ�ɂȂ����Ă���A���邢�͎�����f�����ɂȂ��Ă���B�������\�����l�ɂƂ��Ă��������͓I�ŁA�R���[�W���Ȃ�ł��ˁB�f�Ђ������őg���킹�Đςݖ�����Ă����悤�Ȗ{�̓ǂݕ����ł����B���������A�ŏ��ɏՌ������s�[�^�[�E�u���b�N�́w�Ȃ�X�q�ƊԈႦ���j�x���A�ςݖ؍H�݂����Ȃ��̂�������Ȃ����Ǝv������ł��B����ŁA�l�̒��ʼn�������葱���铮�@��������܂����B

���ꂩ��܂���������葱�����ł����ǁA���ꂪ����āB�����ȂƂ���Ɂu���o�����Ă���v��100�{���炢�莆�����������ǁA�قƂ�ǃ_���ł����B�ł�1�����A�q�ǂ����ꂩ��Ԏ���������ł��B��������������ŁA����Ă������ȂƎv�������ǁA�ʐڂŗ�����������B
���ꂪ�s�v�c�ȖʐڂŁA������u�����v���Č����čs������A�����ɖ��҂��S�������Ă��āA����̏�ɏ悹���āu��������v�ƌ���ꂽ��ł��B���͂��傤�ǂ��̑O�̔ӂɁA��O�̑O�Ŏ��Y�ɂȂ閲�����܂��āB���̖��Ƃ����̂��A��ɏオ���Ă������玀�Y���s�l�����āA�l�̎�ɓ���������ł���B�����Ă��̐l���u����ł́A�莆��������v�ƈꌾ�����B����ōj�����̂������グ���āA�ł��S�R�ꂵ���Ȃ��̂Łu����A���ꔲ�������Ȃ����ȁH�v�Ǝv���ē���āA30���[�g�����炢�ォ�痎���āA���n����Ƃ����͕���Ȃ�ł��B�ŁA��ϏO�����芅�������Ă�Ƃ������ł����B�u����͂������݂��Ȃ��v�Ǝv���Ă��炻��͐����ŁA���̗����ɐ��ɕ���ɗ�������Ă����킯�ł��B�ŁA���̖��̘b��������A�����ɗ������B
�ꓯ�F�i�j
���R�F����ōs���Ƃ��낪�Ȃ��Ȃ�������āA�������_�����ȁA�����͉������Ȃ��ȂƂ��������ɂȂ�������������܂��āc�J���r�U���Ƃ�Ȃ��������A�S�R�s���ĂȂ�������w������d�b���������Ă��āA�u�e�X�g���Ȃ�������A�����ފw���v�ƌ����āB���Ō��ł��傤���Ȃ��������ǁA�r�U�̖�������������e�X�g���āc�B
���̂Ƃ��A�����ςȕa�C�ɂ��������������ł��B�܂�����Ȃ��B���ꂩ�琸�_�I�Ȃ��̂��Ǝv����ł����ǁA�b���B���Ԃ�Q�ĂȂ����炾�Ǝv����ł����ǁA�ϑz�܂ŏo�Ă��āB���o�A������������������ł��B�����炶�イ�ɂ����Ȃ��̂������邵�A�����Ȃ��̂��������邵�A�d�ԂȂɏ���Ă��Ȃ��B���Ƃ������S�̑܂Ȃ������l����ƁA���e�����Ă��Ȃ����Ȃ�Ďv������ˁB�̏d�͌������Ⴄ���A�h�{�����݂����ɂȂ����Ⴄ���B
����ʼn����̂��������Ńp���ɍs���āA�z�e���ɔ��܂�����A�O�ɏo���Ȃ��Ȃ����������ł��B�ϑz���Ђǂ��āA�H��������ς����܂����B�������ꂵ�������ł��ˁB�z�e���ɑ��������ł����ǁA������Ƃł��������炻�������э~�肿�Ⴄ���Ďv�����݂������āA�������Ƃ�Ȃ��Ȃ����������ł��ˁB�ł��A���鎞�Ƃɂ������J���Ă݂悤�Ǝv���āA�p�b�Ƒ��J������ł��ˁB
����������̏o�����������Ƃ������ԂŁA���̉��ɏC���@�݂����Ȃ̂������ł���B���̉��������p�`�ŁA���ƂȂ��ۂ���ł���B���̊ۂ��Ƃ���ɓ��̌����������������Ă����B�ǂ����Ă���Ɓu���A����͕ǂ��v�Ƃ�������������B�����������Ă���ڂ̑O�ɑ��g�������āA���̑��g�����Ă���Ɓu���A����͑��g���c�v�Ƃ�������������B�����̖ϑz�⌶�o�E�����̋��x�����A���������u���̂̋��x�v�Ƃ����̂������������܂����B�u�����ɂ��̂�����v�Ƃ������Ƃ��A�����̌��o�⌶���̋��x�����͂邩�ɂ����������B���������̐_��̌��݂����Ȋ����ł����ˁB
���Ƃ��Ή����ŃX�g�[���[�Ƃ��A����̖L�����Ƃ����Z���Ƃ��A����Ȃ��̂��́A�����ɂ���������̂��o��������B���i�̓x�[���ɕ����Č����Ȃ����ǁA���̃x�[������蕥���āu���A�R�b�v������v�Ƃ������������Ƃ̋��x�Ƃ������̂������ŒT�肽���Ȃ��Ǝv������ł��B
�l��̉����͂悭�������Ȃ��Ƃ��g�̐����Ȃ��Ƃ���������ǁA�����ɉ�������A�l������A���Ԃ�����A�����������o���ɏo�������ȂƎv���܂����B����͖l�̒��ŁA�w�Ȃ�X�q�ƊԈႦ���j�x��u�x�������̗c�N����v�A���ꂩ���ɂ������e�����邱�ƂɂȂ�O�����[�o�[�̕���ɂ�����u���v��A�}���^�[���[�̕���ɂ�����u���ԁv�Ƃ��������Ȃ����Ă��āA���������̌����ł�����Ƃł����������邱�Ƃ��ł���A��������͉�������Ă��Ă��������ȁA�Ƃ���������������ł��ˁB
�����A���������ő�����͖̂���������ȂƎv���āA���o����ɂȂ�܂����B�������Ȃ�̐l��������ł����ǁA�������L�����A�̂���p���̉��o�Ƃ����܂��āA���̃h�C�c�l�ɂ��ĕ������Ă��������ł��ˁB�ŁA�傫�Ȍ���ŃI�y��������肵����ł����ǁA��������Ɓu���A�Ȃ�قlj��o���Ă������̂��v�Ƃ��킩���Ă��܂����B�����Ŏ����̉ۑ�Ƃ��Ďv���Ă����̂��A�e�N�j�b�N�Ƃ����@�����̂܂ܐ^����̂͐��߂悤�Ǝv���Ă���ł��B�����������낭�Ȃ��̂��Ƃ��A�ǂ��������ƂɎ������s����������̂��Ƃ������ƒ��ӂ��Ă݂悤���ȂƎv���āA�m�[�g�ɂ����ς������o���Ă��B�ł��A�����Ɖ��o�������Ă�ƁA�������ɖO���Ă����Ⴄ��ł��ˁB����Ŏ����ō���Ă݂悤�Ǝv���č��ƁA�s�v�c�Ȃ��Ƃɂ��̉��o�ƂƓ����悤�Ȃ��̂����ł��Ȃ��B�������z���炵�Ċ��S�ɃR�s�[�Ȃ�ł���B�e�L�X�g�ǂu�ԂɁA���������`�ŕ���ɂ��悤���Ă����C���[�W�����S�ɐ搶�̐F�ɐ��߂��Ă�B�������{�l�����o���������B���̊Ԃɂ��ɂ��̂������z�������������ł��傤�ˁB�t�ɂ��ꂭ�炢���Ȃ��Ɗw�ׂȂ��̂�������Ȃ���ł����ǂˁB�ł��Ƃɂ������ꂪ�h���āA�������̐l�̂Ƃ���ʼn��o��������͎̂��߂悤�Ǝv���܂����B
���̌�A����܂Ŏ������������߂Ă����������Ȃ��Ƃǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��Ǝv���āA�Y�Ȃ������Ă݂悤�Ǝv������ł��B�������낭�Ȃ邽�߂̕��@�݂����ȃm�[�g�͂����ς�����̂ŁA�����S���Ԃ����Y�Ȃ��A��̓�T�Ԃ��炢�ŏ������������ł��ˁB
��������܂��V�����W�J�������āA��������c����̂Ƃ���ɑ�������A�v���f���[�T�[���Љ��āA���̃v���f���[�T�[����A���������ă����h���ł�낤�Ƃ������b�ɂȂ�܂����B���ǂ���͒f���Ă������ɂȂ����������ł����ǁA���̃v���Z�X�̒��ŁA�u���A����͂�����������܂�����Ă����邩�ȁv�݂����Ȋ������N���Ă�����ł��ˁB
���̌サ�炭�h�C�c�ɂ�����ł����ǁA�Ȃ��Ȃ��J���r�U�Ƃ�Ȃ��āA�p���Ɉ����z�������ȂƎv������ł��B�搶�����Ƃ��Ǝ�Ƀt�����X�Ŋ������Ă����l�����A�������ɍs�����Ǝv���āA�ו���S���p���̗F�l��ɑ�������ł��ˁB����ŁA�ꎞ�A���̂���œ��{�ɋA������ł��B�������炻�̂܂ܓ��{�ɋ�������������B���̉ו��͂��Ԃ�S���Ƃ�ꂽ��Ȃ����Ȃ��B

�����������f�ނɂ����܂킵�Ă��炤
�{��F���ꂩ��͂����Ɠ��{�Ŋ���������Ă����ł���ˁB
���R�F�����ł��ˁB�h�C�c�ɂ����̂͒ʎZ5�N���炢���ȁB�A�������̂�98�N���炢���������ǁA����Ń[���̏�Ԃɖ߂����悤�ȋC�����܂����B�ł��A�[������ł��S�R�ł���ȂƂ������G��������������������ł��ˁB����͂��Ԃ�Y�Ȃ��������������Ǝv���܂��B�t�ɁA�����Ȃ��Ƃ��납�炢�낢�����Ă������Ǝv���܂����B�ŁA�ŏ��V�A�^�[X�Ŕo�D���[�N�V���b�v�����炭����āA���Ă��Ă��ꂽ�l������2002�N��PortB������������ł��ˁB
���[�N�V���b�v�����ƁA�ŏ��͂����ς��l�������ł���B�����ǁA����u������ɗ��Ă�̂��v�Ƃ����b�ɂȂ��Ă���B����͓��{�̉�������ɂ��ʂ���Ƃ��낪������ǁA�o�D�̖��Ƃ����̂͌��\�傫���ł��ˁB�ނ�͂��܂莞�Ԃ��Ȃ���ł���B����ɗ����Ƃ����̎d���ɂȂ����Ă�������A�����ɂł�����ɗ��������B������1�̕�������Ԃ������č���Ă����Ƃ����̂��Ȃ��Ȃ�����B�e���r��f��ɋ����̂���l�������������A����ɗ��̂�1�N�A2�N��Ƃ������ƂɂȂ�ƁA���܂�c��Ȃ��ł��ˁB����Ă邱�Ƃ����Ȃ���ꂾ�������B�����PortB����������Ƃ��Ɏv�����̂��A������u�o�D�v����Ȃ��āA�ꏏ�Ƀv���Z�X�����L���Ă����悤�Ȑl�ƁA�v�����낤���f�l���낤���W�Ȃ�����Ă��������ȂƂ������Ƃł����B����������A�c���Ă��ꂽ�l������Z�\�������Ă�l��������ł��ˁB�f�����Ƃ��A���y���Ƃ��B�ޏ��i�Ŏq�L�j�����Ƃ��Ɖ̎肾�������B
�ŏ�����uPort B�Ƃ��Ă��������������������v�Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�^����ꂽ�A���邢�͗^����ꂽ�g�g�݁A�\�Z�I�ȏ����ɍ��킹�āA�����������ʼn����ł��邾�낤�H�ƍl���Ă����̂��A�l�ɂƂ��Ă͂������ǂ������B
�v���ʂ�̂��ƂȂ�ďo����͂����Ȃ���ł��B���҂ɂ������ė~�����Ǝv���Ă��A�S�R�Ⴄ���������Ԃ��Ă��Ȃ��B�����������Ƃ��������ȂƎv���Ă��A�\�Z�I�ɂ͑S�R�o���Ȃ��B���������A���ʂ������瑫�����Ɗ�����悤�Ȃ��Ƃ��������V�N���������A�������납�����B
���̒��ł��낢��H�v����ƁA�������C���[�W���Ă������́A�����������Ǝv���Ă������̂����A��肭�������ꍇ�ɁA�����Ƃ����Ƃ������낢���̂��o����ȂƂ��������������Ă�����āB����͂����A���̕����ł������Ǝv���܂����ˁB��肭�����Ȃ��A�s���R�ȏ��t��ɂƂ�悤�ȕ����ł������ƁB
�悭�u���o�v�Ƃ����ƁA�S���m���ĂāA�F�Ɏw�����o���ĂƂ����A�����闧��݂����Ɏv���邯�ǁA��������Ȃ��āA���Ԃ�̒��ň�ԍŏ��ɂ����܂킳��鑤����Ȃ��ƁA����ĂĂ��������낭�Ȃ���ł���B���ԂĖl���������Ƃ̌J��Ԃ��ɂȂ���������Ƃ����̂́A�l�̃C���[�W�݂����Ȃ��̂��A�N���ɂ�点��Ƃ��A�������g���Ď������悤�Ƃ��Ă�������B�����Ȃ�ƁA�l�̗͂Ȃ�Ă������m��Ă邩��A�������Ƃ̌J��Ԃ��ɂȂ��Ă��܂��B��������Ȃ��āA���҂���Ƃ��Ƃ��h���}�g�D���N���A�l��g�ݗ��Ă�B�l�������܂킳��Ė���Ⴄ�`�ʼn���������āA���ꂪ����ɔ��f�����B�����獡�́u�l�^���s����v�Ƃ��������Ƃ͑S�R�Ȃ��ł��ˁB�����قLjႤ���̂��o�Ă���B�f�ނ��Ⴄ�̂œ��R�Ⴄ���̂��o�Ă���B����������ŏI�I�ɂ܂Ƃ߂Ȃ����Ⴂ���Ȃ��̂ŁA�����ł�����Ƃ��������o�Ă���̂�������܂���ˁB
�g�g�݂Ƃ��Ƃ����ׂĂЂ�����߂āA���������������܂킳��Ă���B����V�������������邵�A�u����Ȃ̏o������������v�Ƃ�������������܂��ˁB���̊Ԃ́w����ʍs�H�x�������Ȃ�ł����ǁA�ŏ����炠�������������悤�Ƃ͎v���ĂȂ�������ł���B�X������Ă��āA���̓X�������낢�ȁA�����ȁA�����������Ɏ��������̂ق����h�������e�݂̂����ɂȂ�B��������ƁA�X�����Ă���������őg�ݗ��ĂĂ�����Ȃ��A�X���玩���������g�ݗ��Ă�ꂽ�Ƃ������o�ɂȂ�B��������ƁA����ȂɈ������̂ɂȂ�Ȃ����A���Ƃ������낭�Ȃ��Ȃ����Ȃƍl���Ă����ł��B

�w�z���e�B�l�x(c)Yuichiro Tanaka
�{��F�Ŏq�L����Ɨт���́A�ǂ�������������PortB�Ɋւ�邱�ƂɂȂ����̂ł��傤���H
���R�F�܂��ޏ��́A�O�Ɍ��c�݂����Ȃ̂Ɋւ���Ă����Ƃ��������Ėl�����܂��܂����Ɋւ���āA�o�������ł���ˁB�l�����傤�ǃh�C�c����A���Ă��Ă�����Ƃ��Ă��炾�������ȁB
�Ŏq�F�����B�m���ꎞ�A����炵�̂Ƃ����ȁB���͑�w���ォ��Ȃ�ƂȂ������Ƃ̊ւ�肪�����āA�����͋������������̂̊����𒆐S�ɂ��Ă�����ł����B98�N���炢���ȁB
���R�F�h���}�g�D���N�̗т���̏ꍇ�́A�l�炪�w�z���e�C�l�x�Ƃ����̂�����Ă����Ƃ��ɁA���܂��ܓ������낢��Ƌ��͂��Ă���Ă������c����Ƃ����c���̐l�ɁA�l���h�C�c��̂ł���l���~�������Č����Ă���A�т�����Љ�Ă��ꂽ��ł��B�ŏ��́A�ނ̓p�t�H�[�}�[��������ł��B
����������ˁA����ς�ނ͑����ł���l�ŁA�������h�C�c����ł�����ǁA����ȊO�̂ق��������ɂ͌��\�d�v�������肷���ł���ˁB
�h���}�g�D���N�Ƃ����̂͂ƂĂ��������ĂāA���Ƃ��Ζ|��҂Ȃ�Ďv���Ă����肷�邯��ǁA�|��҂͑��ɂ����Ƃ��āA����Ńh���}�g�D���N��������Ă����̂����ʂȂ�ł���B�ǂ������d�������̂��Ƃ����̂��B���łˁA�l�͂Ȃ�ƂȂ��h���}�g�D���N�Ƃ����������d���̌o�����������邯��ǁA�\�l����Ώ\�l�Ȃ�ɂ��낢�낢���ł��B����Ŗl�����������̂��u���������̂����肾��v�݂����Ȋ����ŗт���ɓ`����ƁA�ނ�����Ɏ����ł��낢�����Ă����B�܂��h���}�g�D���N���Ă��̎��̊m������Ă��Ȃ�����ǁA�����ނ͊����̂Ȃ��ŁA�����ō���Ă��銴�������邩��A���������\�͂������Ă���l�����h���}�g�D���N�Ȃ�ł���ˁB��������Ȃ��Ɩ{���ɖ��܂�Ȃ����A�^�������Ă��̌^�̒��ʼn��������Ă������Ƃ���Ȃ���ł��B�ނ͂����������Ă��āA�w�j�[�`�F�x����{�i�I�Ƀh���}�g�D���N������Ă�����Ă��܂��B

�w�j�[�`�F�x
�{��F�т���́A����܂ʼn��������Ȃǂ͂���Ă���ł����H
�сF���₢��B���܂��Ɍ���ł��ŋ��݂��̂���10�{�Ȃ����炢�ł���B�S�������Ƃ��ւ�肪�Ȃ�������ł����ǁA���Ƃ��Ɛl����u�����������Ƃ��Ă݂Ȃ��H�v���ėU����ƒf����Ă����K�����Ȃ��āA�ŏ��ɍ��R����ɐ��������Ă�������Ƃ����A�����Ȃ胁�[�������āA�u�o�Ă��������v�ƌ����āA�u���Ⴀ�o�܂��傤�v�Ƃ��������ł����B����Ōm�Ï�ɍs������A����͂��̐l�����ʔ������Ƃ���Ă�Ȃ��Ďv���Ăт����肵�āA���������}�ȎQ����������ł����ǁA���ł�����Ǝv���Č��\�����܂������傱���傱���o�����肵�Ă���ł��B�ł��ʂɉ��������邱�ƂȂ��A���������̎���Ă����Ԑ��Ȃ�ł���ˁB����Ŋւ��悤�ɂȂ��Ă����܂����B
�܂��h���}�g�D���N�Ƃ����Ă��A�h�C�c�ł̃h���}�g�D���N�̗��j�I�ȈӖ�������I�ȈӖ����A���Ƃ��Ƃ���Ȃɏڂ����Ȃ��ł����A���{�ō��ǂ������ӂ��Ɏ�e����Ă��邩�Ƃ��A�ǂ������ӂ��ɋ��߂��Ă邩���Ă��ƂɊւ��Ă����ɏڂ����͂Ȃ���ł����APort B�ɂ�����h���}�g�D���N�Ƃ����̂͂ǂ��������̂ł������炢���̂��Ƃ������Ƃ͏�ɍl���Ă܂��B
���̂Ƃ���l���l���Ă��Ԃ����܂��Ȓ�`�Ƃ����̂��A�o���オ�������̂Ɋւ��ĐӔC�����͉̂��o�̍��R����Ȃ�ł���B�ł��o���オ�点��͖̂l�̐ӔC�B
Port B���Ė{���ɑ�R�����Ȑl�����āA�����������Ⴉ�߂����Ⴉ�Ȃ�ł��B���R����������Č����āA���Ⴀ�F��������܂��Ƃ����̂���Ȃ��āA�����F�������ȃA�C�f�B�A�o�����A������o���邵������o����Ƃ��A���ꂪ��肽���Ƃ������ς��ł��ł���ˁB�����ȕ������ɂԂ��肠�����N�����Ă�B
�F�ɂ͂�肽�����Ƃ������ς������Ă�����āA����������܂łɂǂ��ɂ����q����ɊςĂ��炤�������Ɏd�グ��̂��l�̐ӔC�B�ł����q����ɊςĂ���������̂Ɋւ��Ă̐ӔC�͍��R����A�݂����Ȋ����B���͂�������Ď��g��ł܂��B
���R�F�Ⴆ�X�P�W���[���ɂ��Ă��A���������x��Ă�Ƃ��A�������l�߂Ă��Ȃ���܂�����Ƃ��A���������̂�ނ��S���`�F�b�N���Ă܂��B�����̌m�Â͖l��3�l�ł����ǁA�f���̐l�Ƃ��͂܂��ʂ̊������Ă�킯�ł���B���������Ԃ�r�܂Ƃ��s���ăC���^�r���[��f�����B���Ă��邵�B�l�͂���ɑS�R�������Ȃ����A�ނ�͏���ɍl���Ă���āA�����������ʂ��o���Ƃ������Ă���������Ă����ł���B������������������A�S�̂̐i�s���ǂ��Ȃ��Ă��邩�A�l�͂킩��Ȃ���ł���ˁB�����ނ͍��A�S���������Ă�B
�Ŏq�F����A�u�o���v�ƂȂ��Ă�͎̂��ЂƂ肾���Ȃ�ł��B�ł�����͓��ɁA�����������ȗv�f�����w�I�ɂ���B
���R�F�h���}�g�D���N���Ă����ƃv���f���[�T�[�ł������ł���B�e�v���W�F�N�g���Ƃɂ��̐���������ɂǂ������ł��Ĕ��f���Ă����A�����čŏI�I�ȕ���̏o���Ɋւ��Ă��A���������Ƃ����ア���炠�����͂�����Ƃ܂�����Ȃ����Ȃ��Ƃ��A���Ə����S�̂������Č��n���Ă����B����̌����͂��̂��������l�ȗv�f������̂ŁA�h���}�g�D���N�Ȃ��ɂ͐�ɐ��藧���Ȃ������ł��ˁB

�w����ʍs�H 〜�T���^�q�R�ւ̗�〜�x(c)�ǔ��V��
�l�ɔC����������ɂ������̂��ł���
���c�F�l�͑O��́w����ʍs�H�x�̂Ƃ��ɂ���`�������Ă�����āAPort B�̒����������Ă��������ł����A�����ł��������L�@�I�ɐl�����т��Ă���Ă����̂�������ۂɂ���܂��B���ꂪPort�@B���ے����鍂�R��������A�q���Ă���т�������A�������͊Ŕ��D�̋Ŏq��������A�������͒N�ɏے�����邩�킩��Ȃ����ǂ����Ȑl�������܂Ƃ߂āuPort B�v�Ƃ��������͋����ł��ˁB���Ɖ����Ƃ��A�[�g�Ƃ��ł��肪���Ȃ̂��A�A�[�e�B�X�g�������𒆐S�Ƃ��Ă���Ă����W�c���Ǝv����ł����APort B�͏W�c�̂��肩���Ƃ��Ă��Ɠ��Ƃ������ς���Ă���Ȃ��Ǝv���܂��B
�сF������Ƃ��ɁA�L���X�g�Ƃ����̂������o�[��10�l���x�Ȃ�ł����ǁA�r���̃v���Z�X�ł������̔{�ǂ��낶��Ȃ��l�Ɋւ���Ă�����ĂāA������{���ɂ����Ȑl�ƈꏏ�ɂ���Ă��ł���ˁB������u�l�炪�����Ă܂��v�Ƃ��u�l�炪�A�[�e�B�X�g�ł��v�Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA�{����Port B�Ƃ����̂͂ЂƂ̗����I�ȏꏊ�݂����Ȃ��̂ŁA�����ɖ����Ȑl���W�܂��āA���ʂƂ��č�i�Ƃ����̂�����ꂽ���̂���Ȃ��āA�ꏊ�Ƃ��Ă̌��������܂��A�����Ă��q�����Ă܂������ɏꏊ�����܂��B�������������Ȃ�Ȃ����Ɩl�͎v���܂��B
���R�F���ƁA�l�Ɛl�Ƃ̌��т��Ƃ����̂͂ˁA�}����������d�v���Ǝv����ł���B�W�c�̂��肩���Ƃ��ĂˁB���ꂪ�l�������炾�߂Ȃ�ł���B���ł��Ȃ�����i�ł��Ȃ��E�E�E�F�̊Ԃɉ����������āA�����ʂ��Ă��̐l�ƌ��т��Ƃ��������B�l�Ɛl�Ƃ̊Ԃɋ�Ԃ�����������ƁA�g�D�Ƃ��ďW�c�Ƃ��āA���邢�͐l�ԊW�Ƃ��ċ������Ƃ�܂���ˁB�����ō����Ă����F�̋��ʂ̗����Ƃ����̂��ł��邵�A����͂������厖����Ȃ����Ȃ��Ďv���Ă܂��B
�������f�ނƂ��āw�_�B�ƁB�x�Ƃ����e�L�X�g��������ǁA�e�L�X�g�Ǝ�������������Ă邱�Ƃ̂��̊Ԃ��炢��Port B�������Ȃ����ȁB������F�������ւ���Ă�����Ȃ����Ǝv���܂��B���S�ɂȂ�̂����\����ۂȂ̂��\���݂����ȂƂ���ł��ˁB���ꂪ�l�ɂȂ����肵�Ȃ��̂����\������ł���ˁB��̂ǂ�Ȍ��c�Ƃ��ł����S���l�ɂȂ����Ⴄ��ł���B����͂ǂ����ĂȂ낤�ˁB
�Ŏq�FPort B�́u�v���W�F�N�g�����v���Ƃ����̂��v���t�B�[���ɏ����Ă������������������ǁA���ł��Ȃ�V�������̂ɕς�����肵�Ă��܂��B�ЂƂЂƂA�V�����v���W�F�N�g�ɂ�����������������āE�E�E�Ⴆ��������A���͂��������̂�肽�����炱�������ӂ��ɂ���Ă�Ƃ��A����Ɍ������Ă����������ׂ��肷��l�����邵�A�f�ނɑ��Ă��ꂼ��̃A�v���[�`�����Ă��܂��ˁB
�сF�F�A�E�\�Ƃ�������傪�����ł����ǁA����ł����̐�債�����Ȃ��Ƃ����킯����Ȃ��B�����������̂��̂Ɏ����������ˁB�������Ȃ���������ł��������Ă����̂��F���y����ł�Ǝv���B���Ƃ��Ƃ̃t�B�[���h�ɂƂǂ܂��Ă����Ȃ��Ȃ��ł��Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ��Ă����������āA�F����傩�炿����Əo�āA�݂͂����Ȃ���ЂƂ̂��̂�����Ă����̂͂Ȃ��Ȃ��V�N�ŁB����F�V�������Ƃ�����Ă��ł���ˁB�����疈��ʔ����Ǝv���B
���c�F�{���Ƀv���Z�X�����L���Ă���Ă������Ŏ������Ă邩�痝�z�I�ł���ˁB
�Ŏq�F���o�����������̂��Œ肵�ĂȂ�����Ƃ����̂�����܂��ˁB
�сF����A���ꂪ��ԑ傫���ł��ˁB�����Ƃ����A�N�����āu���o�Ƃ����S�ɂȂ���̂��v���đO����܂���ˁB�����獂�R����������_�̒��S�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��āA�����Ă��������������Ƃ��Ă邩�炢����Ȃ����ȁB
�Ŏq�F���o�Ƃ������̂��ǂ��������̂��Ƃ����̂�T��Ȃ������Ă��邾�낤���A�F�����ꂼ��̎d��������Ă����Ă��邵�A�����g��������Ă����̂͂Ȃ��A�������Ă���悤�Ȋ����ł��ˁB�T��Ȃ������Ă����āA����łȂ݂�Ȃ����L���Ă��āB
���c�F���������Ӗ��ł͓��ʂȃR���[�W�����ł��������Ă����Ă��ł��ˁB
���R�F����͎��R�ɂ��܂������Ă܂��B�l�H�I�ɂ�낤�Ƃ���Ǝ��s����B����͎����ł��킩���Ă܂��B�^�Ƃ����R�Ƃ������̂��厖�Ȃ�ł��B
�{��F���R����̔������f���Ă���ƁA�{���ɂ����������̂ɓ�����Ă��܂���ˁB
���R�F�{���ɑ厖���Ǝv���܂���B�����ˁA�ǂ���i����肽�����Ă���܂苭���v��������ƁA��R���g���[���������Ȃ��ł���B��������Ȃ��āA�{���͐l�ɔC�����ق���������ˁB�l�ɓ�����������ɂ������̂��ł���B������������R�Ƃ����낢�됶�܂�Ă��邩��A���ꂪ�������ł���BPort B���n�߂Ă���́A���������Ӗ��ł����ƑR��ׂ����ɑR��ׂ��������N�����肾�Ƃ��A�n�v�j���O���N��������R���N������o�����������A�����Ƌ@�\���Ă���Ɗ����܂��ˁB�����炪�����r�����Ȃ��ŁA����ɗ�����Ă�������Ƃ����Ԑ��ɂȂ��Ă���A�}���l���Ɋׂ邱�Ƃ��Ȃ��ł��Ă�����Ȃ����Ȃ��ċC�͂��܂����ǂˁB
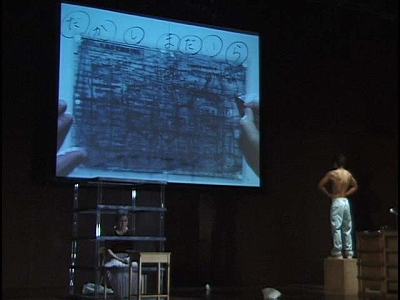
�wMuseum: Zero Hour�@J.L.�{���w�X�Ɠs�s�̋L���x
�{��FPortB�̌������݂�ƁA����ō���������c����t�B�[���h���[�N���Ă����������A11���ɑ�D�]���������n���ʂ�ł́g�c�A�[�E�p�t�H�[�}���X�h�w����ʍs�H�x�̂悤�ȍ�i������A����Ńu���q�g��n�C�i�[�E�~�����[�́u�����i�I�j�e�L�X�g�v�Ɏ��g���䂪����܂��B�Ȃ��A���ɑΏƓI�Ȃ���2�������ɕ��s���Ď��g��ł���̂ł��傤���H
���R�F����͋��R�Ƃ����v�f�������ł��ˁB�w����ʍs�H�x�ɂ��Ă��A�w���c��x����鎞�ɁA���܂��܉��c�F�̖{���Q�l�œǂ�ł���B�ǂu�ԂɁA�u����͊X�����̃p�t�H�[�}���X���ȁv�Ƃ��������������Ďn�߂���ł��ˁB�ŏ��ɒ����̂悤�Ȃ��̂������āA������t�H���[���Ă����ƍ�i���ł����Ⴄ�B�����獡�A�`�Ƃ��Ĉꉞ��ɕ�����Ă��邯��ǁA�ǂ����ɂ��Ă��l���u���������H������肽���v�Ƃ������́A�����o��݂����Ȃ��́A���̏o��ɑ��锽�����A��͑O�q�I�ȕ���A��������X�̒��ł̃C���X�^���[�V�����݂����Ȃ��Ƃ����Ƃ������ƂɂȂ��Ă܂��ˁB
�Ŏq�L�F���ʓI�ɂ��������`�ɂȂ��Ă����Ƃ������A�ŏ����炱���������ɂ����ƌ��߂Ă��킯�ł͑S�R�Ȃ��ł��ˁB
�сF����ς�A�l��͑f�ނ��u�x�z����v�Ƃ������͖l��̕����e�����Ă����܂킳���Ƃ����̂��D���Ȃ�ł��B�����l�����Ƃ��A�u�X�v��������u����ȃe�L�X�g�v���A�l��̗͂���ǂ��ɂ��x�z�ł��Ȃ��B�����Ȏh�����āA�l�炪�v���Ă��݂Ȃ������悤�Ȃ��̂������オ���Ă���Ƃ��������������Ȃ����ȁB��������R�̂悤�ŁA�l��̊�{�I�ȍl���������f����Ă���̂�������Ȃ��A�Ƃ����C�����܂��ˁB
�Ŏq�L�F�ŏ��ɁwMuseum: Zero Hour�@J.L.�{���w�X�Ɠs�s�̋L���x��������Ƃ��ɁA�u�{���w�X����낤�v�Ƃ������Ƃ͌��܂��Ă�����ł����ǁA������ǂ��������ɂ�邩�͂킩��Ȃ��B���ꂪ�A�}�Ɂu���������v�Ƃ������ƂɂȂ��āB���͍s�������Ƃ��Ȃ�������ł����ǁA�u���������Ԃ����炨�����낢���ƂɂȂ��Ȃ����v�Ƃ������ƂŁA�t�B�[���h���[�N�����邱�ƂɂȂ�����ł��B
���R�F�{���w�X�����Ƃ��ɂ��A�Ȃ��{���w�X�Ȃ̂��Ƃ������R�͂��܂�Ȃ��āA�����������������Ȃ�ł��ˁB��������ɂ��������o�Ă��āA�u���͉�������v�ƕ����ꂽ��ł��B�l�͖��̒��Łu�{���w�X�����v���ē�������ł��B���܂ł���Ȃ��Ƃ͑S�R�l�������Ƃ��Ȃ�������ł����ǁB����Ŗڂ��o�߂āA�u����A���Ⴀ���̓{���w�X���ȁv�݂����Ȋ����ť���B
�ꓯ�F�i�j
�����ł������Ȃ���������肽��
���R�F���Ԃ�A�������Ƃ����̂����Ŏv���������Ƃ����ƁA���l�E�|���V���Ƃ������o�Ƃ����āA�ނ����{�ɗ�����A�������ē�����Ƃ��������Ă�����ł���B�ǂ����ē����悤���Ȃƍl���Ă�����ł����ǁA���܂�v�����Ȃ��B�����͓����ʼn���������Ă��Ȃ���A����܂肻�������ӎ��͂Ȃ��ȂƊ����܂����ˁB�t�ɓ����ł������Ȃ������݂����Ȃ��̂��A�ǂꂾ���ӎ����č���Ă���낤�Ǝv���ƁA�S�R�Ȃ��ȂƎ����Ŏv������ł��B����Ń{���w�X�ɍ��������Ԃ��悤�Ǝv������ł��ˁB���ō������Ȃ̂��͂悭�킩��Ȃ����A�Y�ꂿ��������ǁB
�ł�Port B�̊����́A�l���h�C�c�ŕ����Ă������Ƃ������ăh�C�c�I�Ǝv���Ă��邩������Ȃ����ǁA�l�̋C�����Ƃ��Ă͓��{�ł����A���邢�͓����ł������Ȃ��悤�ȉ�������肽���Ƃ����C�����͂����������B�t�Ƀh�C�c�̏͂�����x�킩��̂ŁA�h�C�c������������Ə�肭�ł���Ƃ����悤�Ȃ��̂������ς������ł��B����͈�Ԃ̃l�b�N�Ȃ�ł����ǁA���{�̌��㉉���͕̏n������ł��B����͂����I�ɂ����������A������������l�ޓI�ɂ�������������Ȃ��B�ł��A�����炱���o���邱�Ƃ�����Ɩl�͎v���Ă܂��BJ�����c�W�����N�����ł���ˁA�l�͂����������t�Ŋ���̂͂��܂�D������Ȃ�����ǁA�ł�����͈�ʂł͂������^����˂��Ă�ȂƎv���Ă��āA���S����Ƃ��������܂��B���{�ł���Ă���ȏ�A�W�����N����Ȃ����_�������A�Ƃ����͖̂l���������������Ă��܂��B�ł����̏o�����݂����Ȃ̂͂����Ԑl�ɂ���ĈႤ���A���̏o�������u��邢�V�[���v�Ƃ��u���炾�炵�������v�Ƃ��A�����������Ɉꌳ�����Ăق����Ȃ��B�����ǁA���̍��{�I�ȃR���Z�v�g���͎̂^�����Ă܂��B

�w����ʍs�H 〜�T���^�q�R�ւ̗�〜�x
�{��F���{�ɂ����āA�������u�W�����N�ł������肦�Ȃ��v�Ƃ����̂͂ǂ��������Ƃł��傤���H
���R�F�����ł��˥���A���Ƃ��ΐ���ʂŌ����ƁA�u��������v�ƌ�������̂ŁA�h�C�c�̌��ꂩ����{�ɂ�����̂͂������������Ă���悤�Ɍ����邵�A���ۂ������������������Ă����ł��ˁB����Ɠ����y�U�ō���Ă��˥���B���ꂩ��ނ�ɂ͋���V�X�e���������āA��������⎄������ɓ�����҂͌����Ă���B�����������҂���9������17���܂Ōm�Â��āA�قږ��ӌ���������B���������̂��J��Ԃ��Ă������肭�Ȃ��ł���B���������A�{���̃v���̔o�D�Ƃ����̂��w�Z�ō���āA����ɓ����Ă�����ǂ�ǂ����Ă����B���������o�Ƃ������玟�ւƌ�サ�āA�ǂ�ǂ�V���������ӂ��āA3������1�{�͐V�������̂����B����͂���ς���҂͈炿�܂���B������1�����ďI��肶��Ȃ��āA���p�[�g���[�V�X�e�������牽����J��Ԃ��o����킯�ł���B�����ʂ�����낤���ǁA�u���i�����v�Ƃ����Ӗ��ł́A���{�ɔ�ׂ��炩�Ȃ肢�����ł��B���{�̏ꍇ�͂Ȃ��Ȃ������͂����Ȃ��B�����^�����āA�W�����N����Ȃ����̂���낤�Ƃ�����A���Ԃ[���b�p�Ƃ������h�C�c�ɂ͐���Ȃ�Ȃ��Ǝv���B100�N�o���Ă���ƒǂ����邩�ȂƎv�����ǁA���̎��͂���ς���������i��ł邾�낤����A���Ԃ܂Ōo���Ă��ǂ����Ȃ��ł��ˁB
�ł��S�����z��ς���ƁA�ނ炪�L�������炱�������Ȃ����̂Ƃ����̂������Ƃ���B���Ƃ��`�F���t�B�b�`���̂悤�Ȑg�̂��Ƃ��A�������̕��@���Ǝv����ł���B
�l��̏ꍇ�́u���T�C�N���v�݂����Ȋ����ŁA������̂�S�R�Ⴄ���̂Ƒg���킹��ƁA����Ƃ܂������Ⴄ�p�������Ă����B�g�̂��Ƃ��A�����Ƃ��A���Ƃ��ΊX���������Ǝv����ł��B�����̏��X�X�͂�����u�Y��ȊX�v�Ƃ��������ł��Ȃ����A���X�X�Ȃ�ĕ��i������Ă�悤�Ɍ�����X���A������Ǝd�|��������āA�����\���I�ɂ��q�������悤�ɂ���ƁA�X�������Ă����B������������Ă���̂͂��q����Ȃ�ł���B���������g�g�݂������A�p����E�B�[���݂����Ȕ������X�ɂ͑S�R�ǂ����Ȃ����ǁA�������������̏��X�X�ł��A�����I�ɂ������������낢���̂ɉ��������邱�Ƃ��ł��邼�Ƃ����Ƃ���ŁA�W�����N�Ƃ������t���g�������ȂƎv���܂��B����͕���ł��������Ǝv����ł��ˁB���䑕�u�ɂ��Ă��A���҂̐g�̂ɂ��Ă��A���ɂ��Ă��A�S�R�������̐l�ƈႤ���ŁA�����ł������܂�Ȃ����̂������Ȃ����ȁB

�w����ʍs�H 〜�T���^�q�R�ւ̗�〜�x(c)�ǔ��V��
�l���W�܂��Ƃ��ĉ������@�\��������
�{��F���̂��b�Ɗ֘A���Ă��邩�킩��Ȃ���ł����A�ȑO�ɍ��R�����Ă������ƂŁA���Ɉ�ې[�������̂��A�u�����͈�̊���������i�Ƃ��Ċς�Ȃ�A���������f��̕����D�����v�Ƃ������Ƃł��B
���R�F����͑厖�Ȃ��ƂȂ�ł��B���̊Ԃ́w����ʍs�H�x�̂悤�ȃp�t�H�[�}���X�Ȃ�ł����ǁA�悭�X���p�t�H�[�}���X�Ƃ����ƁA�p�t�H�[�}�[���p�t�H�[�}���X�����Ă���Ƃ�������q���ς邾���ł���ˁB����͂����ꏊ���O�Ɉڂ��������ł����āA����Ă��邱�Ƃ͑S�R�ς��Ȃ�����Ȃ����Ǝv����ł��ˁB�������猀��ł��Ɩl�Ȃ͎v���܂��B���Ƃ�����A���q����̎Q���ɂ���Ă�����ƕς��A���q����ɒ����Ă��������Ƃ��A���q������A�����A�����Ƃ����̂������̎����ɂȂ�悤�ȑ̌����āA�����������畁�ʂ̉������ςĂ���Ƃ��ł��A�N�����Ă��邱�ƂȂ�Ȃ����Ǝv����ł��ˁB�Ƃ����͕̂����̍�i�������������̂Ƃ��Ă����Ȃ��āA��������q�����̏�ł������������Ԃ����L���đ̌�����Ƃ����̂������̓��ꐫ���Ǝv����ł��ˁB�f�悾�����瓯���t�B�����𐢊E�e���Ō�����B����͎B��ꂽ�ߋ����Ǝv����ł���ˁB���ꂪ�����̏ꍇ�A���g�̐g�̂������ɂ����肾�Ƃ��A���낢�날��킯�ł��ˁB
�����Ƃ������̂͂��Ȃ�Â��Ǝv����ł���B���ꂾ���C���^�[�l�b�g�����B���Ă��āA���܃����h����j���[���[�N�ʼn����N�����Ă���̂����A���^�C���Ŋς�鎞��ɁA�킴�킴�����ЂƂ̏ꏊ�ɑ����^��ŁA���Ȃ����Ⴂ���Ȃ��B�����������Ȃ��B������Ă��Ȃ莞��x��̌`������Ȃ����ȂƎv�����ǁA�t�ɂ����ɉ\�����݂��Ȃ����ȂƎv���܂��B���܃C���^�[�l�b�g�Ȃǂ����ĂĂ��܂Ɏv���̂́A�߂��l�ƁA�����������̐l�������Ȃ���Ȃ����ȁB���Ƃ���mixi�Ƃ��ł������߂��̗F�B�ƃR�~���j�P�[�V�������āA����ȊO���Ȃ��B���邢�́A�j���[���[�N�Ƃ����̂����������̊X���D�������ǁA�t�ɋ߂����̂ɑ��ĊS�������Ƃ��B����Ԃ��ƁA�x�������͑f���炵���Ƃ��������āA�x�������ɏZ��f���炵�����Ƃ����肶��Ȃ��킯�ł��B�ׂ̐l�̑��������邳���Ƃ��A���낢�날��B�����ǃC���^�[�l�b�g���Ƃ����������Ƃ͊����Ȃ��ł���ˁB�������������������������E�ɖl�����͐����Ă�ȂƎv���܂��B�l�͂���������������厖�ɂ������Ȃƍŋߎv���Ă��܂��B
�������߂��g���ł��Ȃ����A�����������l�ł��Ȃ����A���Ƌ߂����ǐg������Ȃ��l���W�܂�悤�ȏ�Ƃ��ĉ������@�\������ꂽ��Ǝv����ł��ˁB�C���^�[�l�b�g�̐��E�Ƃ͈�����������o�A�����G�ꍇ��Ȃ����ǂ��Ƌ߂��ɂ���Ƃ����Ƃ���ŁA�ǂ����������́A�W�c�����܂��̂��ȂƂ����̂́A���ꂩ��̉��������ő厖�ɂ��Ă��������Ƃ���ł��ˁB
�����炨�q������Ă������厖�Ȃ�ł��B�w����ʍs�H�x�͂��������Ӗ��ŁA���q����ƈ�Έ�ŃR�~���j�P�[�V�����ł���M�d�ȋ@��ł����B�{���͂��q������Ĉ�l��l�l���Ă��邱�Ƃ��Ⴄ���A�݂�ȈႤ�͂��Ȃ��ǁA������������Ă���Ɓu���q����v���ďW�c�ő����Ă��܂��B���ꂪ���ŁA�u��i�v�������āu���q����v�����āA�Ƃ����ςȓΗ�����������ȂƂ����̂�����܂��ˁB

�wRe:Re:Re:place 〜���c��ƌË��c��̍s���i�s���j〜�x(c)Yuichiro Tanaka
�{��F�����ЂƂA��ۂɎc�������Ƃ�����܂��āA������܂��ȑO�ɍ��R�����Ă����A�u���������肻���ł�����Ȃ��Ƃ���ɉ����̉\��������v�Ƃ������t�ł��B����͍���̍�i�ɂ��W���Ă��܂����H
���R�F�W�������ł��ˁB����́w�_�B�ƁB�x�̃L���b�`�R�s�[�Ƃ��āu�|���g�E�r�[�A�h�|��h�s�\���̍a�ɒ��ށv�Ƃ����̂����C���p���t���b�g�ɏ����Ă����ł����ǁA�l�͖{���́u�|���g�E�r�[�A�h�|��h�s�\���̍a�ɂ͂܂�v�Ƃ����������B
�ꓯ�F�i�j
���R�F���ʁu�a�v�Ƃ����ƁA�����ɋ���������Ƃ��A�Ȃ��Ƃ�����������ǁA�l��Port B���Ӑ}���Ă��邱�Ƃ͂���Ƃ͂�����ƈ���Ă��āA�u�a�v���������炻�́u�a�v�Ɂu�͂܂�v�Ƃ������������Ă����ł���B
���Ƃ��w���_�[�����Ƃ������l�����āA�ނ͎��l�Ƃ��Ă����łȂ��|��ƂƂ��Ă����ɕ]�������������l�Ȃ�ł��B�����̕����Ō����ƁA�w���_�[�������M���V���ߌ����h�C�c��ɖ����̂́A�h�C�c��Ƃ��Ă͂߂��Ⴍ����ŁA�\�����ςŁA�l�Ȃ��܂��ɓǂ߂Ȃ��B�ł�������x�����~���͂����������]��������ł��A�h�C�c��̐V�����\�����J�������āB�����m���āA�Ȃ�قǂȂ��Ǝv���܂����B
���ʁA�|��Ƃ�����Ƃ́A�h�C�c�����{��̕����Ɉڂ��Ă����ɔ��������{��ɂ��邩�A���邢�͓��{��炵���\���ɂ��邩�Ƃ������Ƃ��]���̊�ɂȂ�܂���ˁB�ł����������|������Ȃ��āA�t�ɓ��{����h�C�c��̕����Ɉڂ����Ƃɂ���āA���܂ł̓��{��ɂȂ������\���ɐ��܂�ς�点�邱�ƂɂȂ邵�A�����ƃx�N�g�����t�ɂȂ�Ǝv����ł��ˁB
�f�ނ̂ق��ɖl�炪�����܂킵�Ă��炤���Ă����l��̑n��p���Ɠ����悤�ɁA�h�C�c��ɓ��{��������܂킵�Ă��炤�ق������Y�I���Ȃ��ƁB���������Ӗ��ōa����肭�ڍ�������Ȃ�������Ă������́A�a�Ɂu�͂܂�v�B�a�ɂ͂܂�����A�Ȃɂ��o�Ă��邩������Ȃ��B�������̂ق������Ԃ����ĂĂ������낢�B

�w�V�A�^�[X�E�u���q�g�I�u���q�g�����Ղɂ�����10��1���^2���̖�1����20���x
�{��F���́w�_�B�ƁB�x�Ƃ����Y�Ȃ́A�`���V�̋L�ڂɂ��ΊO���l�r�˂∤���S�Ƃ������e�[�}�������Ă���Ƃ̂��Ƃł����A���̃e�L�X�g�䉻���悤�ƌ��f�Ȃ������̂́A���{���܂ސ��E�e���Ŏ�҂𒆐S�Ƃ����E�X�����i��ł���Ƃ������A���邢�͓��{�ɂ����邳���̋����{�@�����Ɩ��ڂȂȂ��肪����̂ł��傤���H�܂��A����̍�i�̒��ł����������������I�Ȗ�肪�N���[�Y�A�b�v����邱�ƂɂȂ�̂ł��傤���H
���R�F���Ԃ��������͂����������ł����A�l��̃X�^���X�Ƃ��Ă͐����I�Ȗ���������啶���̖��Ƃ��Ă͈��������Ȃ��Ƃ������Ƃ������ł��B�Ⴆ�Ή����̌��Ƃ������̂��A����͉�������Ȃ���̌��ł��Ȃ��Ƃ������̂ɂ��邽�߂ɂ́A�啶���̐����Łu�����������������Ă��܂��v���Ă��q����ɓ`���邾���ŏI������������ܑ̖����Ǝv����ł��B���ꂾ������_���������������A���ꂾ������l�����ĎЉ�^�����d���ɂ��܂��B
��������Ȃ��āA�l��͂����܂ʼn�����ʂ��ĉ���������Ă����Ȃ����Ⴂ���Ȃ��Ǝv�����A�������ǂ������ӂ��ɗ��p���邩�Ƃ����̂́A�{���ɐ^���ɍl���Ă����Ȃ��Ă͂����Ȃ��Ǝv���܂��B�l����Ԉ������Ǝv���̂́A�Љ�I�Ȗ����e�[�}�ɂ��Ă����������������āA�u���ꂪ���ł��v�ŏI�������A���Ԃ��ς��Ȃ���Ȃ����ȂƎv����ł���ˁB
���Ƃ����̓��{�l�Ƃ������t�ŕ\������Ƃ�����A���{�l���猩����A�A�����J�l�Ƃ����[���b�p�Ƃ��A�t���J�l�Ƃ��̂ق����A�܂��l������e���Ǝv����ł���B�t�ɂ���ς�W������̂��ׂ̍��A�Ⴆ�Β������Ƃ��؍����Ƃ��k���N�A���邢�͂������̃A�W�A�̍����Ǝv����ł��B���ۖ��ɂȂ��Ă���̂̓A�W�A�̍��Ƃ̊W�̕�����Ȃ��ł��傤���B
���Ⴀ���������l�����A����Ȃɉ����͂Ȃ�����ǂ��g���ł͂Ȃ��l�����ƁA���������Y�Ȃ₱����������̏���g���ăR�~���j�P�[�V�������Ƃ�ق����A�����ō�i�Ƃ��Đ����I�Ȗ����A�s�[����������d�v�Ȃ��ƂȂ�Ȃ����ȂƎv���܂��B���ہA��҂͂ЂƂ�ЂƂ荷������킯�ł����A����͂��������l�����ɂ����l�����ۂɗ��Ă�����āA�u�ǂ��������ƍl���Ă�́v�Ƃ����������b�����������A�������Ă���������Ƃ��ċ@�\����]�n���ǂ����܂�����݂����Ȃ�ł���ˁB
�����炻���������̂Ƃ��ė��p����C�����͂��������������āA���������̂��������Ӗ��ł̐�������Ȃ������Ėl�͎v����ł��B�ł��邾���傫�ȕ���Ƃ��Ă̐����ɉ������Ȃ��悤�Ȃ������ŁA�ŏI�I�Ɍ����Ȃ��Ă���������A�r���̃v���Z�X�ł������������I�Ȗ��������ƈ����Ă����������ł����炢���ȂƎv���܂��ˁB���������v���Z�X���S�R�����܂܁A�ŏI�I�ȕ���Ő����I�Ȗ��������Ă��l�͑S�����Ӗ����Ǝv�����A���ꂾ������Љ�^���������ق��������Ǝv���܂��B

���q����ɍ���Ă����Ă��炢����
�{��FPortB�̂���܂ł̌������݂�ƁA����������c����t�B�[���h���[�N���Ă����������A11���ɑ�D�]���������n���ʂ�ł́g�c�A�[�E�p�t�H�[�}���X�h�w����ʍs�H�x�̂悤�ȁA�ƂĂ��e���݂₷���g�߂ȍ�i���������ŁA���ɑO�q�I�œ���ȃe�L�X�g�Ɏ��g�w�z���e�B�l�x��w�j�[�`�F�x�̂悤�ȕ��䂪���邱�Ƃ��킩��܂��B����́w�_�B�ƁB�x�͖��炩�Ɍ�҂ɑ����Ă���悤�ŁA�`���V��q�ǂ��Ă����Ȃ����ȍ�i�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ƃ�����ۂ������܂��B
���������Ƃ��ɁA���Ƃ��w����ʍs�H�x�̂悤�Ȋ��ɂ͋C�y�ɎQ�����Ă��ꂽ���q���A����͊ςɍs���Ă�����Ă킩��Ȃ���������Ȃ��ƍl���āA�s�����������Ă��邱�Ƃ����邩������܂���B���̂悤�ȏꍇ�����ɂ���Ƃ��āA�������������ɉ������b�Z�[�W�����������܂����H
���R�F����͖{���ɑ厖�Ȗ��ł��ˁB�l��͓������������Ă������Ȃ�ł����ǁA�������q���Q�����Ă����ł����Ă����ƁA�������������Ȃ����Ⴂ���Ȃ����A�����Ȃ��Ⴂ���Ȃ����A���Ȃ��Ⴂ���Ȃ����A��������Ȃ��ƃp�t�H�[�}���X�����藧���Ȃ����đO�����ł��ˁB�{���͊ό��s�ׂ͂������������������̂�������Ȃ����ǁA�ł����ꂪ����̕���ɂȂ����u�ԂɁA���������������Ă킩����́A���邢�͂킩��₷�����킩��Â炢���ǂ��������A�݂����Ȃ̂�����Ǝv����ł��B
�ł����Ƃ����̊Ԃ́w����ʍs�H�x�́A�킩��킩��Ȃ����Ă���܂���ɂȂ�Ȃ���ł���B���������Ⴂ������B�{���͊ό����Ă����������̂��Ǝv����ł��B������w�_�B�ƁB�x���ςĂ�������Ƃ����A�ʂɂ킩��킩��Ȃ�����Ȃ��āA���q������Ă��炦����y������Ȃ��̂��Ȃ��Ă�������͍���悤�ȋC�͂��Ă����ł���ˁB�ςāA�킩��킩��Ȃ��Ƃ����Ă������́u���A���̉��Ƃ��̉������т��v�u���������������Ȃ��v�Ƃ�����Ɏ����ŃC���[�W������Ă��������ˁB����͂��q����͓����Ȃ�����ǂ��A����Ȃ������Ă����Ăق����B
���Ԃ�ˁA����͈Ӗ��͂킩��Ȃ��ł���B�l����K���ɂȂ��ăe�L�X�g��ǂ݂܂������ǁA�ƂĂ��S���͂킩��Ȃ����A��킩��Ȃ��Ƃ���������ς����邵�ˁB�ł������t�̌`�ɁA���ꂾ�����炢������Č`�ɂ��Ă��q����ɒ������A���L�������Ǝv����ł���B�ł�����������̂́A���q����Ȃ�ˁB�����E�E�E�����ƌ������H�ׂ�̂��Ȃ��B
�Ŏq�F�������͑f�ނ��o���̂��ȁB
���R�F�ł��������ĂȂ����Ďv��ꂽ��₾�Ȃ��i�j�B����Ƃ��낾�ȁB
�ꓯ�F�i�j
���c�F�l�͑O��́w����ʍs�H�x�ŁAPort B���D��ł邨�q�����𑽏��_�Ԍ���āA���q�������X�^�b�t�Ɠ����悤�ɁAPort B�Ɉ���𒍂��ł�̂������܂����B���R����̐�y�������������ĂāA���̂Ƃ��ɍ��R����Ƃ��b����Ă��̂���ۓI��������ł����A�����킩��Ȃ��Ȃ����Ďv���ĂĖ�������Ă���s�������Ȃ��Ďv�����ǁA�܂��ł�����킩��Ȃ���ˁE�E�E�ł�����͂܂��S�R���������Ŗʔ��������Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ����ĂāA�킩��Â炳�������Ƃ����悤�Ȃ��̂��Ă��q����ɓ`����Ă���̂�����Ǝv���܂��B
�Ŏq�F�������̃p�t�H�[�}���X�́A����ƌ����邱�Ƃ�������ǁA��������Ȃ����������Ă���邨�q��������\���āA�ӂ������ςȂ�����������A�������납�����ƌ����Ă�������肵�Ă��܂��B������A�킩��킩��Ȃ�����Ȃ��Ƃ���ŊςĂ��炦����ȂƎv���܂��B���ꂪ�܂��ЂƂ̉����̉\���Ƃ������E�E�E�B���Ɠ��{���ƁA�����̉\���Ƃ����̂���ʓI�Ɏv���Ă�����A�����Ƃ����Ȃ����ȂƎ����g�������肷���ł��B
���R�F�����ł��ˁB�l�������v���܂��B
�{��F���肪�Ƃ��������܂����B
��Port B�w�_�B�ƁB�x�����ڍׂ�������
��Port B�I�t�B�V�����T�C�g��������
�i2007�N1��31���i���j�@�ɂ��������n���ɂɂāj